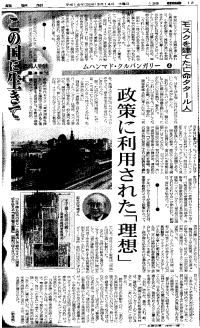 クリックすれば拡大画像 |
|
||
| 開堂式が近づいたころ、軍部や右翼団体から「日本の金で建てた寺院だから、日本人が主宰しなければならない」という声が上がった。 あわてたクルバンガリーは、頼りにしていた頭山満に仲裁を願い出た。たどたどしい日本語で、訴えた。 「これいけません。これ正しくない。これ不正義。これじゃ困る」 陸軍参謀本部の軍人たちは、「何を、外国人のくせにべらべらしゃべりやがって。頭山先生の前で何だ」と、いきりたてた。 困った白ひげの頭山翁は、ただ一言、こう言ったという。 「わしんとこへ持ってくるには、もっと煮詰めて来い」 開堂式を一週間後に控えた五月五日、クルバンガリーは突然、スパイ容疑で警視庁に検挙され、取り調べを受けた。開堂式の晴れの舞台に彼の姿はなかった。新しいモスクの扉を開いたのは、イマームでなくイスラム教徒でさえない頭山だった。イマームにはアブデュルレシト・イブラヒムというタタール人の長老がついた。明治四十二年に来日し、『ジャポンヤ』という見聞録を残したイスラムの重鎮である。 開堂式に続き、庭のテント会場で開かれた祝賀式を、翌日の『東京朝日新聞』はこう伝えた。「先ずイブラヒム翁の開会の挨拶、君が代斉唱、次いで満州国皇帝陛下の御従弟、溥洸氏の発声で『天皇陛下万歳』を奉唱、松井石根大将の発声により『回教徒万歳』を叫び・・・・・・・」 開堂式から一夜明けた十三日午前十時、内務省の外事課長室に内務省、外務省、陸軍参謀本部の三者が集まり、極秘の「クルバンガリー退去処分に関する打ち合わせ会」が開かれた。結論は、国外退去処分だった。 クルバンガリーが追放されたのは、軍部や政府のイスラム政策にとって彼が邪魔になってきたからだ。 静岡県立大学助教授、西山克典(五一)の研究によると、政府の「当面の回教対策」の筆頭は、在日イスラム教徒の団結だった。 しかし、クルバンガリーは当時、昭和八年に来日した亡命タタール人の民族活動家、アヤズ・イスハキのグループとの勢力争いに明け暮れていた。翌九年二月には神田の和泉橋倶楽部で会合していたイスハキ派に、クルバンガリー派殴り込みをかける事件が起きている。在日イスラム教徒は団結とは程遠い状態だった。 さらに、当時の外務省文書はクルバンガリーを追放せざるを得ない理由として、「彼の運動方法は対内的ににして対外地工作を主目的とする回教施策の根本に反する」と記している。クルバンガリーと軍部・政府には思惑のずれが目立っていた。 日本私立大学協会の都竹武年雄(七九)は戦時中、中国の内モンゴルにあった親日政権を支援するため草原に暮らし、日本語教育などの異民族工作を行なった経歴を持つ。 都竹が学生だった昭和十六年ごろ、若林半という右翼の家を訪ねたときのことだ。日本の若者をメッカ巡礼に派遣するなど、独自のイスラム圏工作を進めていた人物である。 「おお、きたか。風呂、入れ。飯、食え」。磊落に迎えた和服姿の若林は、談話がクルバンガリーのことに及ぶと一言、「あいつはだめだ」と切り捨てた。 都竹は自らの体験を元に、「あのことの異民族工作はいかに彼らを日本に協力させるかというだけで、長い目でみて結束を作っていくもうな方向ではなかったのではないか」と指摘する。 クルバンガリーは日本の”宣伝塔”になるために、はるばる亡命してきたのではなかった。彼の目的は、イスラム教を基礎にしたトルコ系民族の解放だった。そのための当面の課題として、小学校やモスクの建設をはじめ、在京タタール人の生活向上をめざして奔走したのだった。それは「対内的」だったかもしれないが、クルバンガリーには当然のことだった。 日本を第二の故郷と定めた四十七歳の亡命タタール人は、十三年六月十四日、東京をたった。下関から玄海灘を渡り、急行「のぞみ」で奉天(今の藩陽)へ。そして十九日夕刻発の特急「あじあ」に乗り継いだ。列車は遼東半島の原野をひた走り二十日、早朝の大連駅に滑り込んだ。 (敬称略) |
|||
| 産経新聞 | |||
