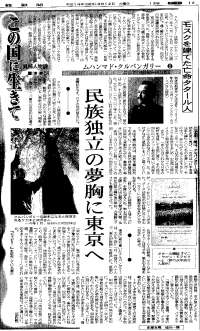 クリックすれば拡大画像 |
|
||
| クルバンガリーは、大隈重信をはじめ政界や右翼の大物と会見して回った。通訳として世話をしたソ連情報活動家、嶋野三郎が、次のような逸話を残している。(満鉄会ほか編『嶋野三郎』)。 後に二・二六事件の思想的な指導者となる北一輝は、クルバンガリーの来訪を非常に喜び、「自分は『日本改造法案大綱』というものを書いたが、その中で、あんたがくることを予言しておる」とやった。北は西欧の侵略からアジアを解放するため、中国西北部にイスラム帝国を作る夢を持っていた。 さらに、「あんたはこれから日本の朝野を啓発して支那に渡り、その西北地区のマホメット教徒を率いて共産ロシアに攻め込みなさい。不肖、北、及ばずながら援助しよう」と語ったという。 帝国主義の時代は、民族主義の時代でもあった。アジア各地の欧米植民地に民族独立運動が広がり、事破れて海外に流浪する亡命者が続出した。その一部は「白人ロシアに勝ったアジアの国」、日本を目指した。中国から孫文が、インドからビハリ・ボースが来た。ボースは新宿中村屋にかくまわれ、「カリー」の製法を伝えたことでも知られる。 「同じアジアの仲間だ」と彼ら「亡命客」を懐に迎え入れ、物心両面から支援したのは右翼の大物中の大物、玄洋社の頭山満や後の宰相、犬養毅らアジア主義者の面々だった。 在京タタール人の長老テミムダル・ムヒト(八二)は今でも、頭山や犬養を「先生」と呼ぶ。 東京に落ち着いたクルバンガリーは、大正十四年一月、仲間五、六十人で「東京回教団」を結成した。新宿の「東京ホテル」二階で開いた発会式には犬養や頭山も出席した。モヒトによると、今の伊勢丹付近にあったその二階建てホテルは、「全室をタタール人が使っていて、満州からきた独身者の溜まり場になっていた」という。 イスタンブールからアラビア文字の活字を取り寄せ、極東初の印刷所を作り、昭和六年四月にはタタール語誌『ヤニ・ヤポン・モフビリー(新日本事情)』を創刊した。この雑誌は七年間、六十号まで続き、海外三十三カ国のタタール人コミュニティーへ送られた。 『モフビリー』を研究している慶応義塾大学教授、坂本勉(五六)によると、雑誌の内容はイスラム教徒やトルコ民族の団結をうたう政治論説、反ソ宣伝の論文をはじめ、日本の生糸貿易や綿織物の輸出状況の記事まで、バラエティーに富んでいた。 「満州国や中央アジア事情、中東のパレスチナ問題の記事もあり、イスラム世界全体に感心を持っていたことがうかがえます」と坂本は語る。記事と記事の合間や表紙には、生け花や着物といった日本文化を紹介する写真も掲載されている。 トタンぶき木造二階建ての印刷所は、渋谷区富ヶ谷の山手通り近くにあった民族小学校の一角だった。小学校は校長のクルバンガリーと職員三人、児童は三十人ほどだった。 昭和二十七年発行の『渋谷区史』に、クルバンガリーが同十二年七月、小学校の創立十周年を記念して生徒を率い、近くの明治神宮にサカキの献木を行なったという記述がある。明治神宮に問い合わせると、「たぶん、これじゃないかという木がありますよ」。晴れた午後、神宮を訪ねた。 本殿へ延びる参道の南端から十メートルほど入った樹林の中、案内してくれた神宮の技師、沖沢幸ニ(五六)は指さした。「六十五年前の記録では、この場所なんです」。高さ六メートル半ほどの茶褐色の常緑広葉樹がすっくと立ち、枝を広げていた。 クルバンガリーは「渋谷を第二の故郷という意味」(『区史』)で、サカキをささげた。故郷を遠く離れて十七年、四十六歳になっていた彼は、日本に骨を埋める覚悟だったに違いない。 (敬称略) |
|||
| 産経新聞 | |||
