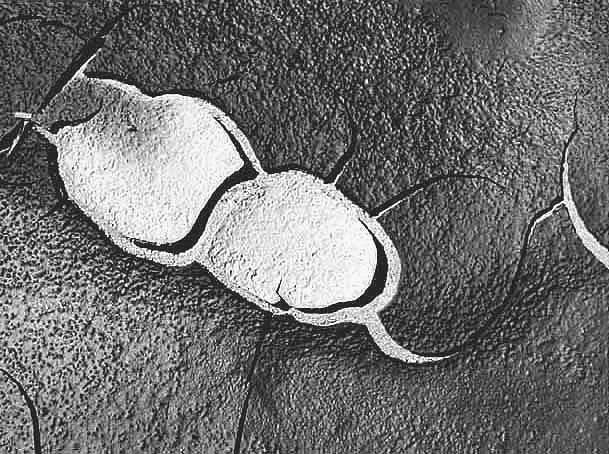五月の光
私の写真で、はじめて世間に出たのがこの作品であった。
俳句に「風光る」という季語があり、「風光り雲また光り草千里」というのがあったが、
この写真はさしずめ「風光り雲また光り屋根光る」といったところであろうか。
1945年、敗戦直後から結核で3年間のベッド生活を送ったが、ストレプトマイシン、
ヒドラジットといった特効薬のない時代。自然治癒にまかせた大気安静療法の回復期にやっ
と許されたのが、ゆるやかな散歩であった。ベッドの上でもカメラを離さず、裏蓋を開いて
スリガラスをあて、戸外を映していた私は当然カメラをぶら下げての散歩に出た。
ある日、山近い隣町との境界あたりで、この倉庫のような屋根が五月の陽光に光り輝くシ
−ンを見つけてカメラを構えた。快晴ではなく、薄い白雲を透した半晴の光りはまぶしいよ
うな風景になる。そこへ、偶然にも赤ちゃんを背負って小さな女の子をつれた女性がやって
来た。点景もピッタリで2、3枚のシャッタ−を切った中の一枚である。
実にありふれた光りに満ちあふれた四国の田園風景であったが、何となく写真雑誌に応募
する気になり、四つ切りに引き伸ばして送った。それがそのまま初応募、初入選になり、ア
−ト・ぺ−ジに印刷された。今見るとまったく素人風の写真であるが、光りの化身のような
風景を描くモネの絵が好きだった学生時代の写真はこんなもので、どれもこれも光りが満ち
あふれたものばかりであった。
(入選作品の図柄は、これとは多少異なる。当時は入選作品のネガは雑誌社に送る条件があ
り、ネガから製版印刷されたが、ネガの返却がなかったので、これはその一連のネガから
選んだもの。1949年5月1日撮影。「光画月刊8月号」掲載)
それにしても、この2年後には私は東京に出て、まったく立場を変えて写真誌の編集にた
ずさわり、月例の審査に加わって講評の一端を書く身になろうとは−−−。そのわずか2年
間の私の作品の激しい変貌が、私の進路を変え生涯を写真の世界で送ることになった。
|

 第一回
第一回