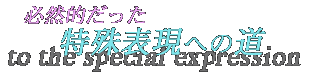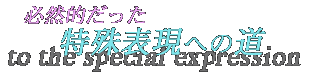この「玉井瑞夫インタ−ネット写真展」は、写真展というよりは明らかに写真入門
講座といった方がふさわしい方向で展開してきた。それはぼくが撮影の第一線を引
いた後は写真によるボランティアをしたいと希っていたことに原因がある。
しかし今回からは、あまり一般的でない少し個人的な技法、つまりぼくが生活の基盤とし
てきた写真の話が主体になる。退屈と思われるところも多くなるが、写真の世界では多少変
わった分野でもあったので、「写真は生誕後、まだわずか160年あまり、小さな出来事の
積み重ね記録が歴史をつくる、目の黒いうちに何でも書き残して置いてほしい」といった向
きもあるので、あと6、7回は勝手気ままながら重い筆を運ぶことになる。
ぼくの仕事は、専門誌の「コマ−シャル・フォト」などで、スペシャリストへの道といっ
た特集記事には、「写真の物理的化学的メカニズムにめっぽう強いので有名。製版用感光材
料を素材にシュ−ルな世界を創る。必然的だった特殊表現への道。−−」などと書かれてい
るがこれはオ−バ−に過ぎる。めっぽう強いどころか弱すぎて、苦労の連続だったというの
が実情であった。でも、「必然的だった特殊表現への道」というのは、正解である。
この「必然的」ということは、カラ−表現では非常に大切なことなので、再度おさらいに
なるが、もう一度箇条書きで述べておきたい。
1940年代、写真における「時間と空間」という問題にふれた人に、ウィン・バロックとモ
ホリ・ナギ−があるが、カラ−写真が生まれた直後に、もうナギ−はカラ−の将来について
示唆をふくめた次の言葉を残している。
「最高の期待はカラ−によるフォトグラムを征服することにある。カラ−・ヴァル−ルの
真の力学的表現は、直接の光の展開による継続と構成が純粋な光学的法則と視覚的基礎によ
って統一されることによって創られる。
そこでは、色彩は物体をあらわすサインやシンボルとしてではなく、それ自体が本来の形
として理解されることになるだろう。このように内容からはなれて、光による色の形を創造
することはたぶん抽象的な映画や静力学的なカラ−フォトグラムの方向に発展させていくこ
とができるであろう。」
画家は写真の発明で、人物や風景をありのままに模写することを追われ、色彩で生きるこ
とになったが、前衛画家瑛九の描く油絵の生の色彩の威力を目の前で、時には天日でも見て
きたぼくには、モホリ・ナギ−のこの言葉は何の躊躇もなくストレ−トに入ってきた。
「色は光の一部であり、光と同じように変化する。この形象をはなれた、変化しやすい光
りを対象として知覚された主観のなかに認識されたスケ−ルが、それぞれの個性を表現する
ようになって、はじめてカラ−写真の芸術が生まれてくるであろう。」ともいう。
先覚者のいわれたこれらの言葉に強いショックをうけ、好奇心の強いぼくはすぐそれをや
り始めただけのことで必然性というのはこのことである。後に、ぼくはごくわずかな期間だ
ったが編集者という仕事についていなかったなら、乱読癖のあるぼくでもナギ−のこの言葉
は知らずに通り過ぎたことであろう、これも運命だったかと思ったものである。
それにしても、こうした問題に興味を示した写真家は、内外ともに非常に少なくて外国で
は、スイスのルネ・グレブリ−という写真家があり、縁あって1966年にはスイス・ガイギ−
社で彼の原画を見ることになった。彼の特殊技法の進捗度はほとんどぼくと同程度で、世界
は広いようで狭いものだ感じた。
< 表現とは、経験の残留物である >
ぼくは60歳のとき自分の写真人生を総括し分析してみた。そして、それまで何となく気
になりながら過ごしてきたマンレイの「表現とは、経験の残留物である。」という言葉を、
慄然とした心地で受け取った。
残留物とは自分そのものであり、分析の結果はエネルギ−を注いで創作に取組んだのは、
25歳から55歳まで約30年にすぎないことがはっきりした。これを10年づつ1期、2
期、3期に分けると、1、2期はあふれるエネルギ−で、<あれも これも>なんでも手を
つけ、3期になると<あれか これか>と自分の願望にランクづけして、選別しながら仕事
をしている。もちろん55歳をすぎても創作はしているが、慣れと技術でいわゆる精緻とい
えるかも知れないが、エネルギ−が不足気味でパンチに欠ける例が多い。
1期が一番エネルギ−に満ち、下手さ加減もまあまあならパンチがあって気持ちがいい。
失敗が許されるのは、若者の特権だなどといっていた年頃である。2期からは写真家協会の
役員などで要領の悪いぼくはずいぶん時間とエネルギ−を取られ体調はいつも疲労気味。
技術的には向上はしてはいるが今ひとつ迫力に欠ける。3期では、口の悪い友人から色気
違いいわれた色彩も渋くなり、どこに出しても一応通用するが、「質は良くても力がなけれ
ば訴えるものは少ない。」と自戒することがままあった。
「作品は経験の残留物である。」ということが身に沁みてわかり、残留物が最後まで魅力
を発揮するのはその作品がもつエネルギ−から発散するパンチとその質であり、それは必ず
しも終局の地点にあるとはいえず、むしろそのプロセスの途次にあることの方が遥かに多い
とぼくは感じてきた。人生にも創作物にも旬というものがある。
芸術家の「終生現役」という言葉を信用しなくなったのは、45歳を過ぎてからであった
が、それは氾濫するおよそ主義という主義への不信にもよるが、思考はもちろんだが感情と
いったその場かぎり根無し草のようなものも信ずるに足りず、純粋な知覚としての非合理的
な機能、感覚の確実性だけを仕事の土台としたからである。
今回は、45歳前後の仕事として多かった「表紙」の一部を題材に解説する。
一目瞭然ですぐわかることだが、技術的には一般的な作品、「デンマ−クの少女」
「カンペコ・プレス」を除いて、他の作品のポイントは、光の3原色(赤・青・緑)
つまり3つの色光によるものである。店頭効果を考えて緑の色光はひかえ気味にして
あるが、加色混合の効果の変化も重要で、その辺は注意して見ていただきたい。
もし、わかりにくいところがあれば、再度 Part18 写真家の色彩学(1)
をゆっくり何回か読めば、理解は早いと思う。
|