part.18 
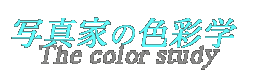 (1) (1)
|
 |
卵 1968
|
ぼくは色の深さを知るほどに、色の専門書を読みあさり、色彩学会の機関誌も送ってもら っていたが先々の流行色の研究や世間より早めの発表記事は、また広告の世界で役立った。 そのうちに、色そのものの表現にも興味を持ち始めた。それはたびたび述べるように、絵 画が抽象期を迎え、物の形だけにとらわれず内面から抽出したものや固有色を離れた色その ものでの構成を試みるようになったことと同じように、僕もカラ−の色そのものでの構成に もトライしてみるようになってきた。 それはある被写体の色をレンズを通してフィルムに移し、それから印刷された色を見るよ りも、フィルム上に、光りそのもの純粋な色光そのものを直接露光する実験である。 この段階では、当然の成り行きから「光の3原色」青(B)、緑(G)、赤(R)による 加色混合と「色の3原色」イエロ−(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)との補色関係の 微妙さを作品で表現しようとしたものなど、僕は興味の赴くままに創っていった。 これらを研究し知ることは、一般の撮影でも光の読み方、色のコントロ−ルに最大の威力 を発揮することになる。 たまたま、「コマ−シャル・フォト」という写真家やデザイナ−、これらの学生、TVC M制作関係者などが購読する専門誌があり、その中に写真の専門的な技術を紹介する「CP テクニック」というコ−ナ−があったが、ここに僕のこの時期の実験的な作品についての記 事が掲載されている。 解説者は、当時の新進気鋭の写真評論家、「吉村伸哉」氏である。氏は秀れた評論家であ ったが、写真評論だけではあきたらず、自らも前衛的な季刊誌「写真映像」というユニ−ク な本を出版していた。この本の徹底した映像へのこだわり、内容の確かさにぼくは惚れ込ん でいたが、僕の解説をしたしばらく後に年若くして他界され、将来を期待されていた写真評 論家だけに非常に惜しまれた。 写真に限らず、絵画でも一般に美術評論家の評論が文学的な表現に終始する主観的な独白 に過ぎないのは、「色のものさし」で寸法を測らないことにあることを、稲村先生が嘆いて おられたが、吉村氏は色彩の理論にも精通し、僕が会った評論家でこれらの点で信頼のおけ る人は、美術評論家の針生一郎氏と彼の2人であった。小林秀雄氏の色彩論は解説の仕方に 少し無理があった。 そんなわけで、吉村氏の解説は論理的で、キ−ポイントをはずさず、的確な説明がされて いるので、彼に敬意を払いこれを僕の解説に代えさせていただくことにした。 これらの作品とそのバリエ−ションは、後に各地でのぼくの個展に展示されたが、いわゆ る玄人好みといわれ、一般以上にプロの間で評価された。 以下は、写真評論家・吉村伸哉氏の解説をそのまま転載する。 |
|
 |
3つのタマゴ 1968
|
 |
トレーシング・ペーパー 1968
|
 |
チューリップ 1968
|
カラ−・チャ−ト ◎これは、研究資料として作成した玉井専用のカラーチャートである。
|
|
ここでは、専門用語はさけて、一般向きの解説をする。 これは、透明なモノクロ−ムのフィルムに、最明部(白)から最暗部(真黒)まで、絞り でいえば半段差の20の階段状になった帯状の白黒のチャ−ト(ステップ・タブレット)を 使い、その下にカラ−フィルムを置いて、上から色光を与えて作られたものである。プリン タ−その他の機材は、写真製版用のものが多く、感材も製版用も多種多様、ぼくの暗室は印 刷所並になった。 白黒のチャ−トの濃淡は、濃度計で測定して数値的にわかっており、色光の露光も0,1 秒差まで厳密に記録されたものを作るので、このチャ−トの応用範囲は非常に広い。 チャ−トの基本的なものは、製版用のカラ−フィルタ−からはじめるが、その露光比を変 えることであらゆる色を出せるから、自分に必要な基本色のカラ−チャ−トを作れる。 次に、何回もの色露光では能率が悪いので、舞台照明用のカラ−ゼラチン・フィルタ−で のカラ−チャ−トも作っておくと便利であった。 この制作には相当な手数と費用がかかる。つまり、カラ−フィルムにもデ−ライト、タン グステン用の別があり、メ−カ−別に多種多様の発色特性があり、また照明用のカラ−ゼラ チン・フィルタ−はメ−カ−ごとの色彩、濃淡があるから大変な種類になる。消費フィルム はあっという間に、100枚、200枚を越える。新しいフィルムやゼラチンが出る度に増 加し、整理も大変である。 研究所は別にして、当時写真家でこんなことをやっていたのは、スイスのルネ・グレブリ と僕ぐらいのもので、現在もあまりいないのではなかろうか。 ぼくは、このカラ−チャ−トと濃度計を手元におき、いつも参考にしてきた。 その効用は、工業的な厳密さを除いて、僕は写真に必要ならあらゆる色彩をカラ−フィル ム上に、即座に作り出せるようになったことである。特殊表現ではこれは必須の制作上の条 件であり、資料である。 撮影上では、構成時の微妙なカラ−・バランスに、敏感に反応する感性が磨かれる。 僕はこんなことをしているうちに、それ以前よりは自分が関心を持った多くの絵や写真の 色彩を識別、記憶する能力は、かなり上昇したように思った。 しかし、カラ−バランスは難しい。創作では、色盲のようなアンバランスなことは、よも ややるまいと思うが、単なる良いカラ−バランスさえ保てば良い作品になるとは限らず、ギ リギリのバランス、息をのむようなバランスともなれば、難しさはいいようがなく、僕はま た全く初心者のようなものだなと感じ、生身の色の道も難しいようだが、相変わらずカラ− の色の道も果てしないものだとよく思う。 |
この写真をクリックすると 色の基本的な解説があります。