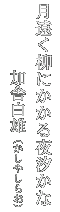part.16 
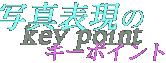
< 造形の基本を見直そう >
ぼくは、講座で自己主張、個性ある写真への道をいいつづけているが、このところの質問
や関連するHPをみて、基本としての物の見方、特性としてのシャ−プネス、グラデ−ショ
ンの重要性への理解が、今一息不足しているためのミスを発見することが多くなった。
そんなわけで、迷路にはまれば遠回り、過った暴走は無駄な努力に過ぎずということにも
なりかねず、今回は色の話をするつもりだったが、急遽、確認の意味での提言をすることに
した。といって、そんなに堅苦しい話ではない。
|
|
グラデ−ションと密度
光の強弱を、そのまま非常に敏感に写真に定着・表現できることは、写真の特にすぐれた
能力であるにもかかわらず、恵まれ過ぎておろそかにしている写真が多過ぎる。
絵画も音楽もグラデ−ションの表現なしには成り立たないが、中でも書はその表現が一番
技術的にむつかしい。そこで書におけるグラデ−ションの有無がどれほど影響を及ぼすもの
か、これらを具体的に示せば、理解しやすいのではないかと考えた。
ぼくは、ずいぶん長く講義をしてきたが、「書」で解説するのは初めてである。
「 かな 」 について
奈良時代には漢字の楷・行書をもって表され、「かな」としての姿が整えられつつあった
いわゆる「万葉仮名」を用いた遺品が知られているが、「かな」は漢字を省略化、簡略化し
て生み出され展開したわが国独自の文字である。
10世紀後半には、「男手」、「女手」、「片仮名」など仮名の書体を示す名が見える。
後に平仮名と呼ばれた「女手」の仮名は、各文字を連続させて書く連綿体をもちいながら、
墨の線の美しさを発揮させ、優雅で流麗な書の世界を完成させた。
能書として著名な藤原行成(972〜1027)らが活躍し、「源氏物語」を著した紫式
部や「枕草子」の清少納言ら才女が輩出した藤原文化の全盛期には、「古今和歌集」に代表
される和歌は、教養の大きな要素であり、生活とも深くかかわっていた。これらをいかに優
美に書写するかにも大きな関心が払われていた。
ディスプレイとしての条件
ここに引用した書は、現代の「かな」の第一人者といわれる熊谷恒子氏の名作である。
読むだけの手紙なら、墨の色は単に真っ黒で形よく書かれたものでもよかろうが、この場
合のように大きく半切(135 × 35 cm)で展示される場合は、読むだけの文字を越えて、デ
ィスプレ−として鑑賞に耐えるもの、つまり遠くからも眺め、近寄っても見る展覧会の作品
としては、それだけの条件・内容・表現がなければもたない。
もちろん、鑑賞に値する写真も絵画もまったく同様である。
この作品には、コミュニケ−ションとして手にとつて読む「かな」文字から、ア−トとし
て鑑賞にたえる「かな文字」への変身を十二分に認識し、グラデ−ションを駆使した密度あ
る表現がみられる。
ところで、俗称「変体仮名」といわれる字がこうした展示には多いが、これは「かな」字
体の歴史的な豊富さと表現のバランス、自由さからのもので、これが何とか読めるのはせい
ぜい僕らくらいの世代までであろう。
若い世代の人には、読めなくてもまず鑑賞するだけから始めればいい。関心をもてば、漢
字の草体からの発生だから、そのうち読めるようになるだろう。僕はよほど気にいったもの
だけ、判じながら読む程度である。
|
|
書における諧調
書には、潤筆というたっぷりの墨で書かれたものと、渇筆というかすれた書き方がある。
「月」という字は、渇筆状で二つの点はゆっくりとやや停滞し、「遠く」は、運筆の緩急
で実に微妙な諧調が表現され、続く「柳に」の繊細な薄色の渇筆も見事である。何度も加筆
できる絵と違って、一気に筆を運んでこれだけの諧調を表現するのは大変なことであろう。
墨の濃度は、真っ黒ではなく何パ−セント位の濃度であったろうか、非常に微妙なト−ン
が見られる。あまりの薄墨では力がなく、真っ黒い墨での渇筆状のかすれは妙味をそえる程
度で、これほど豊富なグラデ−ションの表現は不可能である。
試みに、製版上でリスフィルムによる活版といわれる真っ黒と真っ白の2諧調だけにした
ものを並べて見た。その差は歴然としている。
この匂うような豊麗さで、時空を感じさせた密度ある表現の原因は、その切れ味のよいフ
ォルムの美しさだけでなくグラデ−ションの表現技術にもよることが、写真をやる者には良
く分かるはずである。
これだけ品位があり、優れた造形を見せる書は当代では珍しい。1900年代の代表的な
秀作として残るであろう。
現代の書家のほとんどは、書における諧調の重要さを忘れ、その研究を怠っている。
|

|
「 激 」 須田剋太
字のトリミング
これは、「激」という字である。須田剋太は独特のタッチで黒っぽい絵を描く洋画家であ
る。TVで放映されていた「街道を行く」では、司馬遼太郎との良いコンビで、ひょうひょ
うとした彼の人物と挿絵に、心地よい感銘をうけていたが、字もおもしろい。
これは、いわゆる書家の書く字とはまったく異なる。画家らしく諧調のバランスもすぐれ
ており、書の分類にするものではなく、カリグラフィ−に類し絵に近いものであろう。
「激」という字を、これだけ自由奔放に書き、字の周辺がこれだけ切られたものも少なく、
僕は密度あるトリミングで、はちきれんばかりの表現が、写真にも参考になる例としてとり
あげた。もちろん、状況によってはこれと正反対のたっぷりした空間での構成もある。
「画家は真っ白なスペ−スに絵を描く。写真家はすべてのものが存在する空間から自分の絵
柄を取り出す」といったのはエルンスト・ハ−スだが、例えばもしこの「激」という字がひ
とつの被写体だと考えてみると、どうだろうか。
写真家はこの被写体から受けとる感銘を、どのように構成し表現しようとするだろうか。
題材は何であれ、その作品はその人の人生観(哲学)を現す。すでに講座で僕が話したこと
をもう一度思い出し、また再読してもらいたい。
|

|
< 静物のライティング >
風景写真は、偶然のチャンスに恵まれない限り、自分でライティングを変えるわけにはゆ
行かない。自然が変貌しドラスティックなチャンスを何か月、いや何年も待つて写すという
のは世界的な風景写真家エドワ−ド・ウエストンやアンセル・アダムスの言葉である。そこ
へゆくと、狭い範囲の静物写真ならライティングを工夫しながら、何回でもトライできると
いい、ウエストンはピ−マンを8×10判で数百枚も撮り、発表したのは数枚であった。
|
|
「 ベゴニア 」 矢野昭子(原画)
この写真は、写真講座メンバ−のものである。
これは、露出不足もあって沈んでいるが、もったいない写真である。構成も無駄がなく、
バックも整理され深い青紫のト−ンもよい。これで花へのちょっとした気配り、ライティン
グがあれば、生き返ったような佳作になったであろう。特に前ボケは要注意だ。
大きな風景のライティングは、季節、天候、時間を待つしかないが、わずか数個の花なら
そんなに時間はかからない。日中でのストロボや鏡、レフを使う要領は、人物を美しく照明
するように、人間並みの扱いで、その花の良いところを引き出してやればよい。かなりの美
人でもライティングが悪ければ、欠点が目立つものである。
このベコニアの場合は、花びらの前縁までシャープな質感を表現し、その一部と花芯への
照明でメリハリをつけ、またこの美人(花)のアクセサリ−、副材となっている水滴への微
妙な照明は、これらを真珠かダイヤのように扱ってやればよいという、それだけのことであ
る。その質感と水滴との明暗の対比は、赤一色の画面に精彩をそえることにもなる。
|
「 ベゴニア 」 矢野昭子 (修正分)
僕は作者に断って、この写真に修正を試みた。
僕は、「後一歩という例」として、多少ともこの花を引き立てるため、試みにフォトショ
ップでシャ−プをかけて黄色い花芯にアクセントをつけ、照明不足でさえない花びらの単一
な赤一色のカラ−ト−ンは、シアンを加えて単調さをを救い、全体としては、ややコントラ
ストを上げ、生気を与えようとした。 また、画面のごみや雑物は雑音として消去した。
この修正は、ほんのちょっとした変化だが、表現の強さはかなり変わっている。
しかし、撮影時に凝縮した見方と必然性のあるライティングを、自分なりの個性できっち
りやらない限り、単なる美しさをこえるほどの感性を見せる表現は不可能である。
(ライティングは、花や葉に光を与えるだけでなく、状況により光を遮り、また影をつける
ことも含まれる。)
|
「 ポピー 」 玉井瑞夫
ポピー 玉井瑞夫
これは食事中に、目の前に散ってきた花を見て、太陽光を受けた小さな鏡でメシベ、オシ
ベにアクセントをつけ、空間のバランスをとるために右隅上に少し影をつけて撮ったもの。
もちろん花芯部分のバックはシャド−になるよう配慮した。
この作品は、形にはまらない見方やライティングによる明快さ、全面の質感表現による密
度アップに注意した習作。つまり日頃のトレーニングである。これも弟子や学生たちに勧め
てきた僕流のやり方である。慣れると光が読めるようになり、殆ど時間もかからない筈だ。
撮影でネクタイをしめるような改まった気構えはいらない。さりげなく自然体がいい。
カメラはその辺に転がしておき、気楽に「ハッと思えば写すべし」だ。
ぼくの家のリビングのベンジャミンの幹には、いつもクランプのついたフラッド・ランプ
が止まっており、玄関の傘立には足を伸ばしたままの小型三脚がつっこまれている。
|

|
構成とトリミング
ついでに、構成とトリミングンにも触れておこう。
熟練したプロ写真家は、そのテ−マの写真がどんな媒体による変化にも対応して使えるよ
うな撮り方もする。特にコマ−シャルでは写真の中に文字をレイアウトすることもあり、そ
の余裕もみて撮ることも多い。
ただし、文字をいれる空き間をつくつてあるような写真では、構成的にひ弱くて使い物に
ならない。「A」の写真が余裕のある例だが、右上隅に空間処理としてわずかなグラデ−シ
ョンのある陰影をつけたのがそれである。これが無ければ、単なるホワイト・スペースにな
る。こうした画像は、目的におうじて「B」のようなトリミングでの使用もできる。
Aは明るくてやや軽く、Bはやや重い。構成は、わずかな変化で軽くも重くもなる。
雑誌などの場合は、普通なら横画しか撮らないような横長い被写体、風景などでも扉ペ−
ジ用として縦画も撮っておく。もちろん縦画なりの構成をするが、意外性のあるパンチのあ
る写真ができることがある。風景・静物写真で積極的なこんなトライも勉強になるだろう。
|

|
マクロ・レンズについて
先日、久しぶりに古い友人で、ニッコ−ルF1.4レンズを世界で初めて開発した日本人
として、世界的に著名な掘邦彦氏と話したが、その時花の撮影の話が出た。
堀さんは最近の傾向として、マクロレンズをほとんど開放に近い絞りでピンボケ同様の使
われ方が多いのを嘆き、あれでは質感不足で大伸ばしに耐えられないと心配していた。
(このことはプロの世界では、まず写真が売れないことを意味する)
マクロは、一般レンズが遠距離中心に設計されているに比べ、30〜40cmの近距離の
設計で、新聞紙のような平面の場合、開放でも周辺まで最高の解像力を示す特色があるが、
立体としての花などは前ボケを避けるよう十分な被写界深度まで絞り、画面全体が密度のあ
る描写になる使い方をしてほしいものだといっていた。これはプロの需要に対応した設計者
の立場で、ぼくもには良く分かり、同様に感じてきた。
僕の見方では、前後にピントが合ってきてそれが邪魔になるといった使い方は、構成が悪
いか、構成力がない場合であろうと思う。僕はピントの合う合わないにかかわらず葉や茎も
すべてが密度を上げる副材となるような構成をする。世界の名作といわれる花の作品もすべ
て同様である。戸外などでどうしても非常にシンプルにしたい場合は、黒、白、グレ−、グ
ラデ−ションなどのバックを入れる。
IC用の数百万円もするレンズは、十数枚の構成で、開放で完璧な解像力を示すもので、
まったく絞らず、紫外線に近い波長の照明で撮るといった話もされていた。
ぼくは照明の波長まで指定されているとは知らなかった。そういえば長い波長の赤外線で
の撮影は、確かにピントが悪い。
|

|
回転ドア−の光の反射
1975 エルンスト・ハース
これは、ニュ−ヨ−クのビルの入口の回転ドア−に複雑に反映した高層ビルである。
ハ−スは抽象的な風景を探したのではなく、彼が感じたニュ−ヨ−クのシンボリックな風
景として写したものである。
|
往来 <メキシコティ−>
1963 エルンスト・ハ−ス
ハ−スは、発色の優れた初期のコダクロ−ムの感度の遅いカラ−フィルムを使って、シャ
−プな写真の反対側にあるこうしたブレの実験にも興味を示し、闘牛やヨット、飛ぶ鳥など
多数の作品を残した。
漫画のブレのような画面は、また写真のフォトジェニックな表現でもある。
ただ、動体の動く方向とフォ−カルプレ−ン・シャッタ−の走る方向でブレの形が変わる
ことは知っておく方がよい。
|
文化と文明
「文化と文明」、分かりきっているようで、時々混線していることがある。詳しく言えば
果てしない。ごくごく平易に述べてみる。
文明とは→ 誰でも参加でき、普遍的価値と、そこに便利さと平和を感じることができ
るもの。生活手段を向上させるもの。形あるもの。手で触れられるもの。
(冷蔵庫、テレビなど)
文化とは→ 文化は不合理で特殊なものだが、そこに居れば楽しく心安らぐもの。
文明の普遍性に対して、それに裏打ちされ、また変化する文化は、文明の
反対位置にある。
*文化は個人的あるいはグル−プだけの特異なもの。
精神生活を豊かにするもの。形のないもの。手で触れられない精神的な
もの。個人や民族がもつ習慣も文化だが、他人や他国に及ぼすことはで
きないもの。 (畳に土足では上がらない。襖は座って開くなど)
|
|
ニワトリ
これは、たしかルポルタ−ジュの映画監督、羽仁進氏から聞いた話だったように思う。
彼はアフリカの奥地に分け入り、小さな村で原住民に映画を見せたという。
夜になって、白いスクリ−ンに向かって腰を降ろした現地人は、日本の風景や東京の町並
みが映し出されると、静かに興味を示して見ていた。しかし、彼らが最も興味を示したのは
ニワトリが現れたシ−ンで、ざわめきが起きた。そして左から右へニワトリが走り、画面か
ら消えた瞬間、全員が立ち上がってスクリ−ンの裏側目がけて走つて行き、消えたニワトリ
を探し始めたという。彼らにとって、ニワトリはことに大切な生活必需品だったのである。
こうした人々には、文明、文化の違いから、ハ−スの回転ドア−に反映したニュ−ヨ−ク
の複雑で幻想的な風景や道路の矢印の上のブレた自動車、やや抽象化されてしまった形は、
理解できないだろう。
ア−トの世界での普遍性は、こんなこともあるが、逆にピカソやブラックがアフリカの原
始的な黒人彫刻の影響を受け、自然や人間を単純な形態に還元して描くことから始めたのは
実に興味深いことだ。
|

|