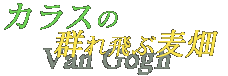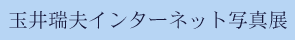part.14 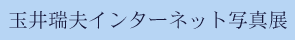
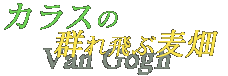
< インタ−ネットとオリジナル >
僕は思いがけないきっかけから、インタ−ネット写真展で作品を見せ、写真表現
の講座を進めることになった。僕はそこで新しい写真の見せ方を知り、また新しい
疑問も持つようになった。そこで、今回は本物と媒体(複製)との微妙で重要な問
題に関連した体験をとりあげて見たい。
僕はやっと半年ほど前からHP(ホ−ムペ−ジ)というパソコンの小さなディスプレイ上
で、本来写真が持つシャ−プさを犠牲にして見せることになったが、反対に日頃見に行くオ
リジナル・プリントの展覧会は全倍サイズが多くなり、その鮮鋭度・ボリュ−ムの差はかけ
離れるばかりで、今後どんな評価・展開になるものか、今のところは判断がつかない。
しかし、当面の問題としては、ディスプレイのサイズが全紙位で、原画どおりの解像力の
ある画面をいつでも見れるようになるまでは、チャンスのあるかぎり本物サイズの原画、つ
まり写真展を鑑賞することを勧めたいと思った。それはHPで見る写真は、その写真が持つ
魅力の半分も表現していないからである。勿論、それは写真をやる以上はいくらかでも上達
し、自分の思想、感情を創作的に表現したいと願っている人達へのことである。
単に自分の写真を、絵日記のようにHP上で見てもらい、友好をはかりたいという人や、
またそれを見て歩き社交辞令のほめ言葉を交わすだけの人なら、せいぜい大キャビネでシャ
−プさ密度に欠ける写真で充分であろう。
絵でいえば分かりやすい。たとえばこの講座で紹介した瑛九の絶筆「つばさ」など天地が
2.6メ−トルの大きさがある。HP上ではキャビネの大きさで紹介したが、これではとて
もあの宇宙的な画面の広がり、油彩のボリュ−ムは伝えられず、また味わえない。サイズに
はそれだけの意味がある。
写真においてもまったく同様である。写真作品の展示には、8×10インチの密着作品も
あれば、全倍サイズの引き伸ばしプリントもあるが、オリジナルにはそれぞれに伴った迫力
がある。サイズと写真独自の先鋭度・密度は、写真表現の内容に大いに関係する。
僕はHP上でよく思う。せいぜい大キャビネ程度のこじんまりした作品を作る要領で固ま
ってしまうと、ディスプレイが全紙になったときその画面を持たせるだけの密度のある作品
ができるであろうか。あと少し視野を広げて本来の写真表現が持つ本質を知り、その方向へ
の努力で、シャ−プでもっと密度がある作品を心掛ければ、美術館などにも収蔵されて世に
残るであろう。せっかくのエネルギ−が勿体無いと時折感じることがある。若い時は二度は
ない。特に20代・30代の過ごし方は大切だ。
この元原稿は、フォト・ディレクタ−概論の一環として、1993年 [Shinc]という
前衛的な写真誌に発表したもので、当時「小林秀雄にかみついた男」といわれたが、そんな
大げさなものではなく、僕の考え方は現在も変わっておらず、今では常識となっている。
一般的な美術批評と各個人へのアドバイスの仕方とは別問題で、これらもむつかしい
問題である。「写真上達への道」の私的・体験的な話は、「裏話」を参照されたい。
|
|
 |
「 烏の群れ飛ぶ麦畑 」 ゴッホ
この絵との出会い
私が初めて見たゴッホのこの絵は、芸術新潮の1951年・新年号にあった。
それは、上質紙に印刷されたモノクロの荒れ模様の空に「烏の群れ飛ぶ麦畑」の絵で、タ
テ5,5センチメ−トル、ヨコ12センチメ−トルはがき半分くらいの粗末な印刷である。
インクの黒はしまらず、ハイライトはネムイ。しかし、この絵の異様な迫力はわかる。
当時、26才であった私の血は騒いだ。心奪われた原因の半分は、さらにその下に書かれ
た小林秀雄の「ゴッホの手紙」という名文にもよる。
これからの話は、ヴァン・ゴッホが死の直前に描いたこの絵について、評論家、作者ゴッ
ホ自身、随筆家などによるそれぞれの立場からの言葉と私の感想である。話の進め方は引用
文が多く、人のふんどしを借りて相撲をとるようなものだが、その方が分かりやすい。
|
複製 「 烏の群れ飛ぶ麦畑 」 ゴッホ
|
その 1
初めて、小林秀雄が見た〈複製画〉について
『小林秀雄全集』 10・11巻より
1947年、著名な文芸評論家であり、絵画の評論家でもある小林秀雄が、上野の展覧会
場でこの絵を初めて知った時の衝撃のシ−ンは、次のように書かれている。
「ゴッホの絵の前にきて、愕然とした。それは、麦畑からたくさんの烏が飛び立っている
絵で、彼が自殺する直前に描いた有名な絵の見事な複製であった。ただ一種異様な画面
が突如として現れ、僕はとうとうその前にしゃがみこんでしまった。」
さらに、感動を次のように記述している。
「熟れきった麦は、金か硫黄の線条のように地面いっぱいに突き刺さり、それが傷口のよ
うに稲妻形に裂けて、青磁色の草の緑に縁どられた小道の泥が、イングリツシュ・レッ
ドというのか知らん、牛肉色に剥き出ている。
空は紺青だが、嵐を孕んで、落ちたら最後助からぬ強風に高鳴る海原のようだ。全管弦
楽が鳴るかと思えば、突然、休止符が来て、烏の群れが音もなく舞っており、旧約聖書
の登場人物めいた影が、今、麦の穂の向こうに消えた−−
僕が1枚の絵を鑑賞していたということは、余り確かではない。むしろ僕は、或るひと
つの巨きな眼に見据えられ、動けずにいたように思われる」。
小林氏は、この日を機会に「ゴッホの手紙」という評伝を書くことになった。
|

|
その2
ゴッホから母への最後の手紙
( No.650 より)
これは、作者ゴッホの言葉である。
ゴッホの残した多くの書簡は、個性的で告白文学とも言える力強い魅力のあるものだ。
しかし、この手紙はあっさりとさりげない。この絵は、その内容にふれたこの手紙が書か
れた日から、3日の間に描かれたと推測してもよいだろう。
「僕が、今、夢中になっているのは丘に向かって途方もなく広がった麦畑のある絵です。
海のように広く、微妙な黄、微妙に薄い緑、除草され耕された土は微妙な紫。花の咲い
た馬鈴薯の緑で、規則正しく仕切られた碁盤縞。
すべては微妙な青、白、桃色、紫の色調をもった空の下にある。これを描いている僕の
気持ちの静けさは、どうやら余りに大き過ぎます」。
「−−では、ごきげんよう。僕はこれから仕事に行かねばなりません。」
(この絵が描かれたのは、1890年7月で日付不明。ゴッホは、この直後、同月の
7月29日、ピストルで自殺した)
|

|
その3
小林秀雄が見た《実物》の絵について
小林氏は、1952年12月から翌1953年7月まで外遊し、5年後にオランダで見た
実物の絵によって、ふたたび、新たな異なった深い衝撃を受けた。記述は簡明である。
「色は、昨日描きあげたように生々しかった。私の持っている複製は、非常に良くできた
たものだが、この生々しさは写し得ておらず、奇怪なことだが、そのために絵としては
複製のほうが良いと、すぐ見て感じたのである。それほど、この色の生々しさは堪え難
いものであった。これは、もう絵ではない。
彼は表現しているというより、むしろ破壊している。この絵には署名なぞないのだ。
その代わりカンバスの裏側には、『絵の中で、ぼくの理性は、半ば崩壊した』という当
時の手紙の文句が記されているだろう。彼は、未だ崩壊しない半分の理性をふるって自
殺した。だが、この絵が、既に自殺行為そのものではあるまいか」。
|

|
その4
大橋良介が見た〈複製画〉について
(大橋良介著 『時はいつ美となるか』
1984年刊より)
ゴッホの絵に対しては、作家、批評家、画家、詩人などがさまざまな角度からの著作があ
る。たまたま大橋氏がこの絵の複製について、小林秀雄が複製と本物を見た時の印象をも引
用しながら、所論を述べている点に注目し、もうひとつの見方としてとりあげた。
大橋氏は建築物から美術にいたるまで幅広く、哲学専攻らしい切り口で、抽象的なエッセ
イを書いている。紙面の関係から、引用は「烏の群れ飛ぶ情景」のある後半の部分だけに限
った。他は、およそ想像がつくであろう。
「ここに『色彩と闇とが逆さまになった絵』がある。それは、単に感性的色彩が天上の永
遠性に否定されたという絵ではない。
むしろ、感性的生命の肯定の極致に現れた破壊的なものの絵である。自己否定の底から
割れ目がのぞく。烏の群れの舞う一瞬は時の内にありながら、この時の割れ目となり、
その割れ目から暗黒の深淵がのぞく。烏の群れはこの底なき深淵の上を目的なしにただ
舞っている。この烏の群れはどこから来て、どこへ去るのか」。
これは、大橋氏の所論「美的時熱の無」という文章の中にある。氏は「この絵は言葉が沈
黙し、美が破れる世界でもある」という。
|

|
ヴァン・ゴッホ 「 烏の群れ飛ぶ麦畑 」 オヴェールにて 1890年7月
その5
私(玉井)の見た《実物》の絵の印象について
(アムステルダムの美術館にて)
1966年6月、待望のゴッホのこの絵を目的のひとつに羽田を出発した。この時、私は
41才、初めてゴッホの粗末な複製を見て血が騒いでから15年がたち、広告写真家になっ
ていた。私は、オランダに入る前に、まずリラックスするように考えた。
ゴッホに惚れたばかりに、これまで知らず知らずに、かなりの人々のゴッホについての評
論の類に目を通して来たので、本当に自分の目を信じて私の五感で「烏の群れ飛ぶ麦畑」に
接したかったのだ。
私は、念願の本物の前に立った。そして、私の頭の中にあったものは、完全に裏切られ
れた。これまで長々と抱いていた陰惨で痛みを伴うような強烈なイメ−ジは、一瞬にし
て飛び去った。それは生々とした初夏の麦畑であった。
その絵からは、まず麦の緊張した黄色が飛び込んできた。複製よりずっと明るい。そし
て全体は純度もあり、力強く、乾燥し、透明さを私は感じた。
私は、とっさに事の後先のことが浮かんだ。「もし、小林氏が複製より先にこの実物に
接していたら、果たしてあのような暗い評論を書いたであろうか」と。ゴッホの表現に
は鬼気は無く、透明で高みにある歓喜に至るものがあるように感じたのだ。
絵の具の厚みは想像していたより薄い。
私は多くの評論家の悲鳴のような印象の代わりにこの絵が陰鬱ではなく、口では言えな
いカラッとしたものを感じ安堵した。ゴッホが狂気の合間に、正気の絵を描かねばなら
なかった異様な人間が出ているのではないかと心配していたからである。
絵は、明るくて強烈、改めて気にいった。本当に来て見て良かったと思った。
私の印象は、多くの評論家とも、尊敬する小林秀雄氏とも大幅に異なる。
私の結論は、『物語りはいらない。専門家は、思い入れが過ぎるのではないか』というこ
とであった。
時に、心理学者、美術評論家、画家などの専門家は、作者の資料調査が行き届きその中に
埋没してしまうのではなかろうか。あまりにその心情を憶測し、絵の造型が示すものより、
心理への感性過敏症になっているように思われたのだ。
これは、この絵を見たその直後の卒直な私の感想である。
|

|
私(玉井)の思うところ
さて、ここまで読まれてあなたは、どんなことを考えられたであろうか。ここまでの内容
をまとめると、
「複製と本物」ということ、それぞれ人による「感性と表現」の差ということ、あるいは「
美術批評」ということについて、あなたはどう感じられたかということである。
以下は提案者として、これらの問題について、私なりの思うままを述べてみたい。断って
おくが私の特徴は、写真家以外は専門家ではないということである。
|
|
1、「複製と本物」ということ
美術を訪ねるとなると世界は広すぎる。だれでもが本物の作品を見られるわけではない。
また特別な例を除いて、本物を見なかったからすべて間違うとは考えられない。
もちろん、本物に勝るものはないが今日は複製技術が進み、複製文化は存在すると思う。
小林秀雄氏の言葉を借りれば、「文学は翻訳で読み、音楽はレコ−ドで聞き、絵は複製で見
る。誰もがそうして来たのだ。少なくとも、およそ近代芸術に関するぼくらの開眼は、そう
いう経験に頼ってされたのである。
翻訳文化という軽蔑的言葉が、しばしば人の口に上る。もっともな言い分だが、過ぎれば
嘘になる。『誰もある一種名状し難いものを糧として生きて来た』のであって、翻訳文化と
いうような一観念を食って生きて来たわけではない」ということだろう。
ところがである。ゴッホの「カラスのいる麦畑」というこの絵に関するかぎり、小林秀雄
の目を狂わせるほど、実物と複製に差があり過ぎた。
私が日本で見てきたこの絵の数々の複製は、確かに小林氏がいうように陰惨な印象を与え
るものばかりであったが、実物は正反対ともいえるほど明るく力強い透明な印象で、狂気の
絵ではなかった。
その原因は、複製時の色の大幅な狂いである。
私は日頃、写真における特殊表現のために、数十種類の色の濃淡をカラ−フィルム上に、
半段絞りの色光を階段状に表現したカラ−チャ−ト(カラ−センシトメトリ−)を自分でつ
くり、それを仕事上毎日のように見ているので、本物と複製の違いがはっきりとわかった。
まず、現場で一番目についたのは、原画の麦畑のハイライトの黄色は複製とくらべて絞り
で1段半以上も明るく、空のブル−との補色関係から明るい輝くようなレモン・イエロ−の
印象であり、原画の空の一部にある白雲を思わせるさわやかなシアン色は、複製では赤みが
多くてシアンのかけらもない紫色のため、重苦しい空になっている。
こんな複製では、今にも嵐を呼びそうな陰鬱な風景になってしまう。本来レモン・イエロ
−もシアンも明るく晴れ晴れとした色相だから、狂った複製ばかり見ていた小林秀雄が原画
を見て、今日描いたように生々しいと感じたというのはよくわかる。
もう3年以上も前になるが、1997年 9月〜11月、 新宿の安田火災東郷青児美術館のゴッホ
展で、この絵が日本での初公開として展示され、私は30年ぶりにまたお目にかかったが、
ハイライトの麦のレモン・イエロ−はやはり昨日描いたように明るく輝き、良い絵はいつ見
ても新鮮なカラ−・バランスを見せるものだと感じた。
入口で売っていた絵ハガキも本国から輸入されていた四つ切大の複製もまったく色違いで
買う気になれなかった。かろうじて本物にやや近かったのが小さな入場券だけで、どんな人
がカラ−・コ−ディネイトをやっているのか呆れたものと思った。これほど原画と複製に差
のあるものは珍しい。
余談になるが、私はゴッホを見た後、英国のブリティシュ・ミュ−ジアムでこれと似た体
験をした。それは奈良で国宝仏を撮っていたころ、美術館で見ていた日本の古めかしい継ぎ
はぎのある埴輪や土器と同じもので、まったく無傷のものがたくさん陳列されており、まる
で昨日できたような初々しさ、美しさがあった。後に考古学者に聞くと、優品はどの時代に
も大切にされ、目のある英国人は良い物だけを世界中からさらっていつたという。
僕はホンモノに如くはなし、本物を見ずしてうかつにしゃべれないものと痛感した。
|

|
2、「感性と表現」の差について
< 小林氏の評伝 >
小林氏の言葉についての感想は私がオランダで直後に感じた結論とほとんど変わらない。
ことに「複製の方が良い」というとろは納得しがたい。
先に述べたように、私は先入観を持って絵を鑑賞することを警戒した。
私はゴッホの手紙に心を動かされ、司馬遼太郎氏が「かれは絶望の底にシリモチをついて
絵を描きだした」と形容したこの天才の悲惨な出発を忖度し、さらに究極のものへのすさま
じい飢渇がゴッホを駆り立てたドラマを感じながらも、「しかし、物語は絵ではない。この
遺産を受け取った人類にとって『死んでしまったら、なおさら作品の中だけにゴッホがいる
と思うしかないではないか』と言いたい。
多くの鑑賞者は作者の裏側の物語を知らなくても、作品だけを対象として見るということ
である。ゴッホが自らを厳しく告白した手紙は、また別の独立した価値あるものだ。
私は再三、小林氏の「ゴッホ」を読みながら、なおも小林氏の表現の中に、思い入れを感
じるのは、カメラというメカニズムを手にする写真家のせいというだけではないと思った。
私には本筋としてあの感覚は生きており、それは今後も大切にしたい。しかし、小林氏に対
して、徹底した抵抗感があるわけではない。そこには、別の価値が見られるからである。
氏の評伝の大部分は、ゴッホの手紙によるゴッホ像の立体化ともいえるものである。その
言葉はただの物語を超え、独立した文学になつており、ある部分はもう詩だと感じ、そこに
は一人の小林秀雄という得難い人間を垣間見ることができるからだ。
|
< ゴッホの手紙 >
あえて私の感想などない方が良いかも知れないが、ゴッホから母への手紙については、あ
の絵の情景を微妙な色彩を挙げながらの克明な文章には画家らしい平静さがあり、小林氏が
いう陰鬱な狂気など私には感じられない。
|
< 大橋氏のエッセイ >
大橋氏の文章は、純粋さと感性があるように推量したが、私にはどうも苦手である。
印象的にいうと、私の性に合う文章は、読むにつれ心の底にしみて行くように感じるのに、
大橋氏の言葉は空をきり、次々とカラスが飛んで行くように消えていってしまう。
大橋氏本人はエッセイであり、試論にして随筆であるといわれるが、この文章はエッセイ
としての節度を持っているのであろうか。卒直にいうと私には、氏のいう「美的時熟」とい
う言葉自体がすでに生硬く、不利ではないかと思った。
その上、こうした論旨は美術愛好者ならすでに大方は理解しているところを、ことさら難
解な言葉で反語を連用し、かえって著者の心理的な戯れ饒舌の空転を思わせた。とにかく私
の浅薄な知識では理解できかねた。
|

|
3、「ある種の美術批評」について
評論のたぐいは一般の人々には、解りにくといわれ、また多少は難しくなければ、有難味
がないと皮肉っぽくも言われる。
これらの意味するところは、感性と知性での武装をやり損なった評論家の中に、言葉の遊
びとしか受け取れぬ難解な評論を展開し、読者に分ってもらう必要を感じない不遜な者や、
視野が狭く分っているのは自分だけといった教祖のような素振りをする者を見かけたりする
からであろう。
こうなると、もう人様に読んでいただくという美術評論そのものを破壊しているのではな
いだろうか。
論理思考ともイメ−ジ思考ともつかぬ浮き草のような小難しい美辞麗句が並んだ自己陶酔
型の評論では、我々一般大衆に理解されるわけには行くまい。野球の投手ではないのだから
変化球で読者を戸惑わす必要はない。言葉は邪魔なものを取り除き、簡明なほど良い。その
ほうが論旨も明確になる。そしてまた批評は中傷、攻撃よりもこれから先への見識や指針と
してのアドバイスの方が大切だと私は思う。
それにしても美術というものは面白い。人間というものの最も不可解でデリケ−トな謎、
それらが形をあらわし、果てしなく微妙に分かるような分からぬような、そんなところに魅
せられるのであろう。ところで、あなた自身は、このゴッホの絵について、どのような見方
をされているだろうか。
さて、今回の話は、人のふんどしで相撲をとることにしていたので、最後にまた小林氏の
言葉を引用しておこう。
「自分の純粋な視覚を信じ、通すことは、易しくはない。でも自分を持つということは、
そのようなものだ」。迷いの否定は人間性の否定につながり、人間を止めなければならぬ。
「迷いを否定したら、美術鑑賞といった貴重な気の迷いを、全く否定しなければならなく
なるだろう」。
|

|
「ひまわり」 ゴッホ 1888年
|
「星月夜」 ゴッホ 1889年
色彩については、<ひまわり>に代表される作品
を「黄色の時代」とすれば、<星月夜><烏の群
れ飛ぶ麦畑」は、「青の時代」といえよう。
|
|
 どちらの絵をクリックしても 「裏話」(写真上達への道) へいけます。
どちらの絵をクリックしても 「裏話」(写真上達への道) へいけます。