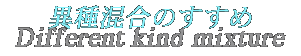「 トータルメディア開発研究所
」への参加
事の始まりは、1970年の大阪万博・テーマ館の岡本太郎総合プロデュサーのサブ・
プロデュサーであった小野一氏が万博の経験を土台として、万博終了後、凸版印刷の肝入
りでトータルメディア開発研究所を創立した時、ぼくも小野氏に乞われてブレーン構成の
一人として参加したことにあった。
「トータルメディア開発研究所」の特色は、文化の事業化、事業の文化化を経営理念とし
て、世界第一級の博物館として注目をあつめた国立民族学博物館や国立歴史民族博物館な
どに始まり、都府県立、市立、企業立博物館、PR施設、博覧会など200以上の文化施設
のプランニング、施工を行ってきたことである。
この会社は創立当時、三つのブレーン組織で構成されていた。
『開発会議』はコンセプト・メイキングで、川添登(建築評論家)、栄久庵憲司(イン
ダストリアル・デザイナー)、黒川記章(建築家)、加藤秀俊(社会学者)、粟津潔 (グ
ラフィック・デザイナー)、小松左京 (小説家)、一柳慧(音楽家)、森政弘(ロボット光
学)、幡野豊次郎(映画舞台美術家)その他。
『十足講』はコンセプトを肉づけするアクチュアル・プランニングで、山口勝弘 (造型
美術家)、伊藤隆康(環境デザィナー)、国東輝幸(グラフィックデザイナー)、丸茂孝
(映画美術、画家)、松本俊夫(映像作家)、氏伸介(照明計画家)、青木保(文化人類
学者)、西原清之(都市計画家)、玉井瑞夫 (写真家)。
『千手講』はアクチュアル・プランに対するテクニカル・フォローといった個別の機能
を発揮するもので、岡田晋(映像評論家)、千葉和彦(日活美術監督)、日暮雅信(作曲
家)、宮井睦郎(光像デザイナー)、水野正夫(ファッション・デザイナー)、その他で
あった。
創業時の役員、ブレーンは30人ほどだったが、その発展とともにブレーン組織は学術
研究者、技術者、芸術家群など約200名になった。
ぼくは、創立時に参加したものの自分の特殊技法の開発や写真家協会の役員などで、超
多忙となり、トータルメディアの方は、充分なおつき合いができずになったが、その胎動
期に参加したお陰で実に貴重な体験、恩恵を受けてきたので、その内容をこの講座で残し
ておくことにした。
ぼくは写真家という職業柄、多くのユニークな方々に接する機会に恵まれたが、万博後
のこの数年間ほどそれが集中した時はなかった。
つまり、ぼくはトータルメディア開発研究所が博物館や美術館の建設を企画し、それら
の品々を世界中から収集し、展示に腕をふるい、さらにそれを絶えまなく新鮮な運営をす
るためのノウハウを研究開発する多種多様な個性あるすばらしい頭脳集団の方々に直接お
目にかかり、お話ができるチャンスに恵まれたということになる。
|
|

|
< 時間無制限の放談会 >
トータルメディア開発研究所は創立されたが、本格的な仕事がはじまる前の準備期間に
時折、お呼びがかかり、当時のまだ漠然とした問題意識をテーマとして数名のメンバーに
よるフリートーク、それは時間無制限の放談会だったが、時に若いゲストを招待してのフ
リートークも実に面白かった。
世間では、テレビによく出てくる人を話題にするが、あれは有名人ということで、すべ
て有能人というわけではない。能ある鷹は爪を隠すとかテレビではお目にかかれないすば
らしいゲストも多かった。
時間無制限については、司会役の解説によると、<それが例えば会社の場合、将来に向
けての方向づけに関して前向きな意思を集約するためには、10人程度で議論する場合、
最低50時間ぐらい必要とされるといわれる。
短い時間の議論は、何度となくしても突っ込み切れず断ち切れとなる。退社後の飲み屋
での議論など2,3時間の議論で得られるのは自分たちの会社が如何にダメであるかとい
う、ダメな点に関するコンセンサス程度で決して前向きのものではない。
なぜ議論が重要かというと、人間はその特性から、いろいろ議論したり話したりしてい
るうちに、自分の頭の中を整理してゆく。黙って考えていては堂々巡りすることでも、口
に出してしゃべることで、考えが整理されていく。最初10人いれば10通りの異なった
考え、見方があったのが、議論を積み重ねていくことで共通のフレームが固まっていく。
50時間、メンバーが本質を突き詰める場を作ることができるかどうかで、その会社が
21世紀に向けて、本当に動く方向づけができるかどうかが決まる。>といったことであっ
たが、多忙なメンバーばかりだから、とてもそんなに長い時間は取れないが、5、6時間
は行われた。
|
|
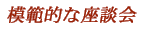
その内容は、もう40年近くも前のことで記憶も薄らいだが、手元に残る『予兆とは何
か』というテーマでの小冊子があり、その出席者は川添登、粟津潔、西江雅之、渡辺格、
小松左京、幡野豊次郎といったトータルメディアのコア・メンバーと社外ブレーンによる
相当長時間の座談会の記録で、これがひとつの基本形を表しているのでとりあげた。
内容については、それぞれその道のベテランであるだけに、中見出しの一部を並べただ
けでも、その話題の豊富さ、スピードの速さなどバラエティがわかるだろう。
中見出しには、「変化と不安のかかわり」、「時間が意味に先行している社会」、「欠
けていた怨念開発」、「情念はオペレーティブだ」、「予兆と自然の摂理」、「釈迦の
『四無記』」、「日本の環境開発」、「文化と生理学」、「エントロピーの増大の中で」
……などとあり、この座談会は、<予兆とは、鏡である>を結論として終っている。
ぼくは、こうしたところへ始めて引っ張り出され、ぼくのいい加減な文化史好みでは、
到底間に合わないほど、底も幅も深く広く、そのレベルの差に、火傷をしそうになった。
また日頃、若い画家や写真家、編集者といった仲間たちとの造形論や常識的な話での遠
慮、会釈のない激しい討論に慣れていたので、先生学者といった方々との穏やかながら厳
しい討論には、いささか戸惑うといったところもあった。
博物館や美術館は、人類の文化史、文明史を知悉していなければ創れない。ここに集ま
った人々はそんな分野の専門家、学者である。そんな人たちとの座談会は史実にもとづい
た共通用語、つまり話し言葉も、とにかく専門用語が多く横文字も多かった。
あの当初のぼくは、写真のことを聞かれると何とか答えられたが、ぼくの方から発言す
る暇はなかった。話を聞きながら、矢継ぎ早に出てくるカタカナ文字を、「ジャック・モ
ノー」「マニエリズム」「ネオテニー」などとメモをするのに忙しく、家にかえると、毎
度、深夜まで辞書を引き、買ったきりで物置にしまわれていた百科事典を引っ張り出して
その用語の歴史を調べるといったことになってしまった。でも、それらを学問としたこと
のないぼくには、正に干天に慈雨といった心境で受け入れられ、ありがたかった。
ぼくは、こうした環境の中で、ジャック・モノーはフランスの分子生物学者で、戦時中
はレジスタンス運動を指導した左翼の闘士でもあったが、戦後は本来の研究者としてノー
ベル医学生理学賞を受けたことや、エントロピーの法則とライフ・サイエンスの大切さな
どを徐々に知るようになっていった。
40代半ばをすぎてこの有様ではと、情けないと思うこともあったが、その傍らぼくは
こうしたトップクラスの学者、先生方の著作に目を通すうちに、「人の声を耳で聞くこと
と文字を目で追うこととは大変な違いがある。」ことに気が付いた。つまり、本の言葉は
公式見解だが、座談が活気を帯びて放談になり、もう一歩その先の、スケールの大きい話
になると本音を漏らすこともある。ということであった。
以来、ぼくは肩の力を抜いて「もっと気楽にやったほうがいい」と、宗旨替えをした。
ある程度リラックスしての参加は、専門分野での表現の違いはあっても、根底では共通
のコンセンサスがあることがわかってきた。
ぼくが門外漢の建築の話で、率直な感想を述べるとそのとおりといわれ、作曲家に写真
のことを聞いても的を射た答えが返ってくるようになってきた。
そんなある日、ふと建築家の黒川記章氏から「写真家のことをカメラマンと呼ぶのは、
失礼ですよね」といわれ、ぼくはとっさに「外国人は自分のことをフォトグラファーと言
い、カメラマンというプロはいないですね」と答えると、「自分の思想、感情をカメラと
いう道具を使って表現するのが写真家」「画家もペイントマン…ではさまにならないね」
といわれた。
ぼくはこの頃、日本広告写真家協会の副会長をしており、会員たちに単なる親睦団体か
ら職能団体への自覚を求めていたので、黒川氏のこのひと言は、まさにわが意を得たりで
共通項を感じブレーンの方々ともよりフランクに話しあえるようになった。
それにしても、これだけの仕事をしてきた人々のほとんどが、ぼくと同年代の40歳代
の若さであったと思うと感無量。小野さんはぼくを除いて万博の人脈資産使いの名人か。
また、それらの個性あふれる人々の経歴をみると、20代で自由闊達、とんでもないこ
とを考え、40代でそれが実るといったことか。文化は波動するとか。ぼくは反省しきり
の日々が続いたものた。
|
|
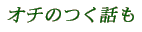
ところで、初めに、「予兆」という活発で厳しい座談会の話を紹介したが、もっと気楽
な放談会もあったので、その一部を紹介しておきたい。
その日のテーマは、まだ始まったばかりの『レジャー』という問題だった。
その当時のお父さんは、休日の度ごとに、子供たちにせがまれて、車であちこちの遊園
地へ連れて行き、子供たちの面倒を見るばかりで丸一日を過ごすのが、典型的なレジャー
だった。
これでは、お父さんは疲れるばかりで可哀相だ。中には、休暇をとって仲間たちとアラ
スカあたりへ鮭つりというレジャーに出かける人もいた。でも、月給の1/3も費用がか
かるのはたいへんだ。
考えてみれば、石器時代の人間は、鮭つりなど日常茶飯事だった。でも、これは生活そ
のものでレジャーとはいえないだろう。
そこで、本当のお父さんのレジャーを考えてみようということになり、以下はメンバー
の一人の答である。
「そこは、ちょっとした広々とした緩やかな傾斜のある芝生で、長椅子に寝て静かに瞑
想している姿がみえる。プライバシーのためには、ちょっとした垣根もいるだろう。
でも、もうひとつ加えたいものがある。右手を地面に近づけるとそこには小さなせせら
ぎがあって、それを指先で感じられるなど、どうだろう? イキなもんですよ」という。
これは、どこかの別荘のようで、大変な金がかかる。「ところで、その金はどうするの
だ」ということで、この笑い話のようなオチつきの放談会はおわった。
もうひとつは、西江雅之氏をゲストに迎えての、金もうけの話などあった。
彼はぼくより14歳も年下の弱冠33歳の青年だったが、その活躍ぶりはめざましかった。
西江氏は、文化人類学、言語学者である。ぼくは言語学者は、世界中を渡り歩いて資料
を持ち帰り、それを整理する仕事くらいに考えていた。
ところがこれが大間違いで、その日の話はベトナムの山奥で場所を変えながら3ケ月、
半年と住みつき、住民と生活をともにしながら、実態を詳しく調べるという大変な仕事だ
った。
ところで、ベトナムの田舎は、1970年頃は生活は厳しく、砂埃りのたつ道路際でわずか
1升瓶一杯のガソリンを1,2本並べて売っている少年たちがあちこちにいるほど貧しい
生活で、これといった楽しみもないわびしい風景であったという。
そんな所でも、憩いの場所には人が集まるのは、世界共通した現象で「ここでちょっと
気の利いた喫茶店を開けば大当たり間違いなし」と、西江氏は思ったらしい。
日本の歴史では、江戸時代は湯屋の二階や床屋は憩いとコミュニケーションの場であり
当今の喫茶店もそんな延長線上にある。ここで肝心なことは、日本とベトナムをくらべる
と、ベトナムはそんな流行が5,6年以上は遅れているということだ。
一歩先を行く日本の喫茶店をサンプルにすれば、ただの喫茶店から音楽喫茶店、同伴喫
茶店などと実験済みだから、ベトナムでのオープニングのタイミングをうまくあわせれば
何の苦もなく成功するというのが、彼の論旨であった。
これらは、いずれもテーマの答えが出た後での付録のような余談だが、ユーモアたっぷ
り、和気藹々、リラックスできるメンバーたちでもあった。こうした環境になれてくると
自分を失わなければ、お互いに刺激を与え合い、また受け合い、それぞれの道での巾をひ
ろげ、厚味をましてゆく。
ところで、こうしてお目にかかった多くのメンバーの中で、ひときわ変わった人がおら
れ、それが観世栄夫氏であった。全く余談になるが付け加えておきたい。
ぼくは、謡曲は下手の横好きだが、能は好きで多くの教えを受けた。観世栄夫氏は世界
に通用する能役者といわれ、新劇の演出家としても有名な方である。
観世さんの声は艶があり鋭くてやさしく爽やかで、すさまじい声量だ。小学校へ上がる
前から鍛え上げた体は、無言のすり足にも激しい呼吸を感じ、いわゆる演技はやらない。
あるがままの人間がそこに存在する感じの舞台である。世阿弥以来六百年のれんめんたる
血のつながりか、どことなく気品のある表情。
そんな印象を持つ観世さんと、ぼくはゴルフで一日のお付き合いをした。トータルメデ
ィアの親睦ゴルフで社長の小野さんと3人が一組だったが、小野さんから観世さんはまだ
あまりお上手でないから、教えてあげてくださいという。
ぼくは、当然これだけの能役者だから、すばらしい運動神経の持ち主だろうと推量して
いたが、それは全く見当違いだった。ぼくは観世さんのスイングを見た瞬間、能とゴルフ
の神経はぜんぜん異質なものだと感じ、全く手がつけられない、教えようもないことを思
い知らされた。
ぼくにとって、こんな経験は唯一無二といったことであった。それはゴルフには全く
通用しない別種のすばらしい運動神経のあることの発見だった。
ぼくは、相変わらず生真面目な話では、火傷をしながら勉強させてもらったが、こうし
た体験を《異種混合》とよび、写真学生や弟子たちにも、同類項だけでの物の見方、考え
方の狭さ、どんぐりの背比べ、孤立からの開放のため、こうしたチャンスには、積極的に
飛び込み、それを生かすよう薦めてきた。また、よい環境は勇気を与えてくれるのだ。
|
|
ハイブリッドな体質
後に、小野一氏は、その著作で粟津氏の言葉として「異種交配は、異化作用を活発に
し、その結果として、異化チャンネルの増加と、クリエイティブ・チャンネルの拡大を
もたらし、相乗的なクリエイティブ効果を発揮する」とのべ、「多種多様な頭脳の掛け
合わせ」と解釈しているとあったが、ぼくは交配とまで行かず<異種混合>でもよいと
思っている。
また、小野氏は、「専門を二つもつことも必要だ。」ともいう。
二つ持つことは、パイ型の人間になるともいう。パイ型人間は、専門分野を二つ持っ
ているので、当然それだけ広い視野を持つわけだが、それと同時に、自分の専門分野の
深さから、他の専門分野の深い内容を類推することもでき、結果としてすべての分野を
深く理解することができるようになる。
我田引水といわれるかも知れないが、ぼくも「写真もいずれやるなら、単なる趣味、
上手下手といったことではなく、自分なりのバックボーンを持った表現を志すだけで、
もう一つの専門家に近づけるのだ。」といいたい。ぼくの先輩、知人には、そんなプロ
並の人が1ダース以上もおられるのだ。
|

「メディアの創造」 小野一著 より
< 説明 >
この会社のシンボル・マークは、奈良の唐招提寺金堂の国宝千手観音像である。
ぼくは、トータルメディアというイメージを象徴するにはドンピシャリなこの仏
像を推奨し、親しい友人である東大寺の佐保山氏に撮影を頼み、そのままでは生
々しすぎるので、ソラリゼーションで手を加え拓本調の千手観音が生まれた。
こんな風変わりなものをシンボル・マークにし、組織名にも十足講、千手講な
どユニークなアイディアを駆使した小野さんは、さすが元映画の美術監督だとぼ
くは感心したものの、国宝佛が一企業のシンボル・マークとして使われるという
のは、実に珍しく、驚いたものである。
このシンボルの使用は、文書ばかりでなく、都心のビル街の地下アーケードに
ある事務所の外壁にも、天井までとどく大きなスーパーグラフィック調の写真パ
ネルとして貼り付けられ、大いに衆目を集めた。マスコミは、新聞紙上で面白い
会社として博物館や美術館を創るトータルメディアの組織を、<千手観音システ
ム>などともじって報道し、仕事が始まる前から話題になっていた。
この観音像の解説については小野さんの名文句がありそれを紹介しておきたい。
千手観音は、正しくは千手千眼聖観自在。観自在とは自力本願の意。『千手千
眼多面多臂』は自主自立と知恵の象徴であり、千手観音の本質を表現したすばら
しい形容語句である。更にこれを企業告知のコピーとしては「千手とは創造の手。
千眼とは情報の眼。多面とは研究の顔。多臂とは事業の力。」と表現していた。
|

|