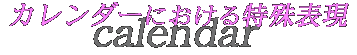part.38  写真表現の多様性
写真表現の多様性
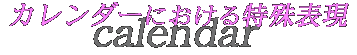 < 現実と写真的現実 >
< 現実と写真的現実 >
ぼくのコマ−シャル・フォトグラファ−としての仕事の初期はデパ−トが大半で、新
聞広告、パンフレット、中吊りポスタ−などの大量生産だった。
それが中期から後半にかけてはクライアントもさまざまで、半分はかなり手の込んだ
ストレートな写真、あと半分がいわゆる特殊表現技法によるものであった。
今回は、カレンダ−を媒体とする特殊表現の一端をお目にかけることにした。
カレンダ−の最終目的は、玉(コヨミ)であるが、インテリアとしてもそれなりの価値が
あるか、どうかが問題である。そこで、タブロ−としての画面も千差万別、製作者は工夫に
工夫を重ねる。毎年のコマ−シャル・フォトのカレンダ−特集号を見ると、なんと味なこと
をやるものだと感心することもしばしばである。
題材は、写真(大風景、雲、山、海、天体、人物、動物、建物、花、魚など)、絵画(油
絵、版画、エッチングなど)、イラスト、デザイン画、古美術、字など多岐にわたる。
いずれにしても、それらは1ヶ月あるいは2ヶ月間を、毎日見ても飽きない作品で、月代
わりのバラエティにも新鮮な変化をとなれば、視覚的、内容的にもそれ相当のパンチが必要
になる。
ここに掲載した作品は、ポスタリゼ−ションによる大阪万博の矛盾の壁の場合とはまった
く異なる。矛盾の壁は煙のノ−マルな原画をハイエスト、ハイライト、ハ−フト−ン、シャ
ドウの4つにセパレ−トして、すべてに色光を露光するために、質感のない抽象的な表現と
なっているが、このカレンダ−の場合は、原画のシャドウ(暗部)のうち、やや明るいハ−
フ・シャドウ(半影)だけをセパレ−トして、その部分だけに色光を露光してある。そのた
め色統一による単純化と自然色による質感が見られるということである。
こうした単純化は人間の普遍的なイメ−ジを浮き上がらせる効果がある。
ところで、この半影といわれるハ−フ・シャドウは、普通のト−ン・セパレ−トでは分離
がかなり難しく、ポスタリゼ−ションを始めて数年後、試行錯誤の末、やっとプロセスの途
中にハ−フ・ソラリゼ−ションを介入させれば分離できることを発見した。
ぼくがこんなことに、しつこく興味を持つようになったのは、ある画集でメキシコの画家
オロスコ、リベラ、シケイロスたちが、革命の理念と深く結びついた壁画運動を始めたころ
の大きな迫力のある壁画作品を見たときに始まった。
この新しい歴史を物語る壁画は、美術館や個人の所有するタブロー画とは違って多くの人
々が、一度に何時でも鑑賞することができる革命後の新しいメキシコ社会建設のシンボルで
あり、国民の求める美術を遺産として遺そうとするものでもあった。
ぼくは日頃、大型のウインド・ディスプレイやまた万博の壁写真を体験してきたことから
普通の写真をプリントしても耐久性がなく、陶板にすればメキシコ並の大作も可能だろうと
思ったのだ。そして、その原画は普通のカラー写真のフル・グラデ−ションでは、昔見た風
呂屋の富士山同様で安っぽく、パンチがなくなることが目に見えており、その写真の骨格と
して、一部は固有色から離脱した色統一をはかれば、陶板による重厚な作品として、壁画も
可能であろうと思ったからである。
大風呂敷を広げた話のようだが、この当時は生真面目に考えていたものである。
これらカレンダ−用の作品はそんな色統一の試作でもあったが、その発表直後、大京
観光のカレンダーに使用された。
技術的な詳しい解説は、デ−タ−も必要で、かなり長くなるのでまたのチャンスに譲
り、今回は思いつくままの感想をのべることにした。
|
「 マロニエ 」
これはパリ−の中心地、大通りに面した数ある小公園のひとつである。
ここは人もまばらで、ベンチには一人の老人が、ゆったりと時間を過ごしている感じであ
った。ぼくは、散々見飽きたシャンゼリゼ大通りやコンコルド広場の写真はかたわらにおい
て、その隣にあるこれといった特色のないこんな小公園の風景を、色彩の統一による<写真
の中におけるパリの現実>といった表現を試みようとした。
現代の画家は主題を明確に描き出すために、色彩が呼び起こすイメ−ジを利用する。画面
の中で核になる色を主調色といい、この色を中心に他の色を展開してゆく。
あらゆる色が存在している世界を固有色を離れたある色に統一すると、画面は意図された
不自然さを生むが、それがかえって命題を鮮明に浮かび上がらせることがあるのだ。
ぼくのこの試作は、原画とくらべ、より単純で、「移ろい」と「かげり」の中にそんな色
彩を見いだしたであろうか。
技法としては、半影(ハ−フ・シャドウ)だけを取り出したマスキングで青紫の色光を露
光した。ピカソはパリで深い青色を見つけ、ゴッホはアルルで黄色を見つけた。それらは彼
らがめいめいの自我をのぞき込んだその奥底に見えた色調であり、その色は彼らには遂に自
分の運命にめぐりあったということであろう。
ぼくは何の色も見つけず、何の理由もなく、知らぬ間に青紫を好むようになっていた。
|
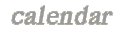
|
サンマルコ (ベニス) 1976
「 サンマルコ 」
このサンマルコ広場は、いつも鳩がいっぱいで、鳩と遊ぶ人々のスナップでもおもしろい
アップのシ−ンが見られるが、このシリ−ズは中景を主体としているので、ずいぶん古めか
しい組立てのような写真機を扱う写真屋さんを中心とした風景を選んだ。
技法としては、全面にハ−フ・ソラリゼ−ションの味わいをそのままにのこした画面は手
書きのリトグラフのタッチを思わせるような表現である。
そしてこの場合に限り、ハ−フ・シャドウによる色統一でなく全面をイエロ−系にし、シ
ャドウは黒では強すぎるのでブラウンにしてある。
この作品は、ぼくの色彩遍歴の中でも一番色をセ−ブした地味なものであろう。
その経過をたどると、1962年ころから始まった色光の実験は、カラ−によるト−ンラ
イン・プロセス、レリ−フ、エッチング、素粒子、ネガ表現などから、やがてモンタ−ジュ
に集中し、67年あたりからはポスタリゼ−ションでの多色によるものが多くなり、70年
の万博前後は色気違いと言われるほどの激しい色使いを経て、76年頃には徐々にセ−ブし
た色使いになっていった。
その間に得たものは、「色ほど複雑なものはない」というひと言である。色は、匂いや味
や音や触感とともに、人間の基本的な五つの感覚、いわゆる五感の一つで物理学や化学の知
識だけでは簡単に割り切れないという事実である。
|
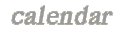
|
ハイデルベルグ (ドイツ) 1976
「 ハイデルベルグ 」
ぼくは、ハイデルベルグという言葉を聞いたとき、アルト・ハイデルベルグという戯曲が
あったことを思い出し、またドイツでは最古の大学がある学園都市といったことから、たい
した理由もなくちょっと寄り道をしたくなった。
何の予備知識も写真撮影の目的もなく訪れたこの街は、息ぬきの散歩に来たようなもので
ライン川の支流という川向こうに見えた真っ白なこの建物を記録したくらいで、それ以上の
記憶はほとんどなかった。
それがカレンダ−の候補写真を選び出す作業を始め、ピンク系の画面にはどんな写真を使
おうかと思った時、なんの変哲もないこのシンメトリ−な建物が浮かび上がって来た。
ピンクは色合わせが難しく、フランス人好みのグレ−との配色はぼくも好きだがカレンダ
−にはパンチが足りない。それで真っ白なあの建物が浮かんだのであろう。
ぼくは、ピンクという名称の元祖だといわれるカ−ネ−ション・ピンクの色光を選び、建
物はやや青みのある冴えた白にした。
|
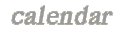
|
ゴンドラ (ベニス) 1976
「 ゴンドラ 」
ベニスには、月日を変えて3度ばかり行ったが、まだ果たしていない仕事がある。
それは、原色百科事典(学習研究社)の編集者から頼まれていたもので、何隻もの船が列
をなして行く海上の葬儀であった。ぼくはそんな風景をチラッと雑誌で見た記憶があったの
で期待は大きかったが、数日の旅行者ではそのチャンスには恵まれなかった。
とにかく、ベニスは写真愛好者のメッカといわれるだけに、フォトジェニックな被写体が
いっぱいで、著名な写真家のユニ−クな表現による数々の名作がある。そんなわけで、はじ
めは6枚組みのカレンダ−にベニスを入れる予定はなかったが、バラエティ上から水ものが
欲しいというクライアントの希望から、こんな無難なゴンドラが加わった。
ひしひしと歴史を感じるこの街の特色は、裏道の狭い掘り割りのような水路沿いの住まい
に見られる。廃船の船板を使った手作りの窓の扉などをぼくは丹念に撮った。どういうわけ
か、この街には猫が多く、窓辺に座ってこちらを見ている「猫のいる窓」といった数点の写
真も残っている。
|
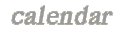
|
オリーブ (スペイン) 1976
「 オリーブ 」
スペインの田舎をさまよう内に、はじめて見たコルクやオリ−ブの木が目につき、何点か
をカメラでスケッチしたが、ある農園で見かけたこのオリ−ブの樹はひときわ大きく、この
農園の主ともいえる貫禄があった。
技法的には、ハ−フ・ソラリゼ−ションでセパレ−トした半影のシャド−である木の影や
凹凸のある木の肌の明暗、葉っぱの一部が色光の露光でブル−になり、地面の柔らかい自然
な枯れ葉色が補色となって、この農園の実感に近い表現になっている。
ぼくは色を選ぶ時、ある時期は、色彩学者が云った「紺は伝統と保守性を、紫は粋と派手
を、灰色はシックな好みを、黄は積極性を、空色は陽気な明るさを、赤は若さと情熱を、朱
は神秘性とエネルギ−を思わせる」といった解説をかなり意識したことがあったが、いつし
か本能的な直感だけになった。
もちろん、色彩学者のこの言葉を否定するということではない。「色は人間の感情を表現
する一つの言葉でもある」からだ。
|
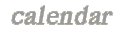
|
ナザレ (ポルトガル) 1976
「 ナザレ 」
ポルトガルの首都リスボンの中心地の一部には、近代的なマンションが立ち並んでいるが
ポルトガルに住む知人の話では、これらの大部分はエリ−トといわれる弁護士、医者、大学
教授などが所有する賃貸用資産だという。
それが一歩郊外にでると子供はハダシで歩いており、そんな子供が案内してくれた一間き
りの民家には、ほとんど家具もなく土間の壁にわずかな鍋がかけてあるだけのキッチンも侘
しく、大都会の狭間に住む人々の厳しい貧富の差を見た。
その後、リスボンから古びたベンツのタクシ−を雇って北へ北へと、田舎らしいひなびた
風物を撮りながら進むと、やがてナザレという港町にたどり着いた。
すぐそばにある丘に上がって一望した時のぼくの驚きは、赤一色に統一された屋根の見事
さで、雑然としたリスボンとは様がわリでこんな整然とした街並みがあろうとは、まったく
予想外のことであった。
ぼくは童話にでもで出てきそうなこの美しい街並みの印象を伝えるために、建物の北壁の
ハ−フ・ト−ンには薄いピンクを、ハ−フ・シャドウには補色のグリ−ンを露光した。もし
これが陶板ならこの渋いグリ−ンは、画面にボリュ−ムをあたえる欠かせない条件になるだ
ろう。
ぼくはこの一日、ポルトガルのピンからキリまで、その表裏の明暗を見たように思えた。
|
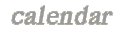
|
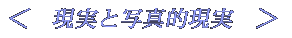
ぼくの特殊表現は、個展などで「どうしてこんな絵のような写真をつくるのか、大変
ですネ」といった率直な質問を受けるが、いつも納得してくれそうな返答ができず苦労
する。ぼくの言いたい主旨を箇条書きにすると、以下のようなことになる。
視覚言語としてのストレ−トな写真は、他のいかなる媒体にくらべても、これ以上のもの
はない。しかし、純粋な意味での現実と写真的現実(写真のなかにおける現実)というもの
の間には大きな隔絶があるということがある。
つまり、われわれが知覚している現実は、多角的な面を持つリズムの中にある生きている
時間の流れとして経験しているが、写真の現実は時の流れの中での一瞬を機械的に切り取っ
たものに過ぎない。
そこで時間を永遠に輪切りにする写真と流れの中にある現実との二つを共用することで一
つの超現実的な効果(リアリティ)が得られるのではないか、隔絶した二つのものの中に、
一つの新しい現実をつくることができれば、それこそ写真として、ある意味での超現実的な
現実ということになるのではなかろうか。
一つの問題として、われわれは体験的現実と写真的現実の中に、何を共存させるかという
問題を発見することで、今後の新しい道が開けるであろう。
色彩のある現実をモノト−ンだけの抽象的な表現にしてしまう白黒写真は、すでに現実ば
なれをしており、カラ−写真の表現で固有色を離れたある色に統一する特殊表現も、隔絶し
た二つの現実からの共用と共存への試みのひとつである。
これらに一つの指針を示したのが、モホリ・ナギ−やマンレイだったのだ。
ぼくはこうしたシリ−ズものの制作をするうちに、「色彩で描くのではなく、色彩が生
み出す効果で描くものだ」といったことを思うようになった。
|
|

|
写真表現の多様性