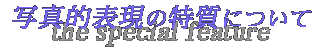 (1) (1)
|
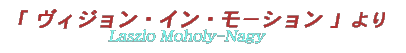
| ||||||||
part.30 
(1)
写真の歴史はまだやっと160年。その丁度真ん中のあたりで大きな変化があった。 この講座の<Part6>で、「新興写真運動とア−ト」に関連してドイツのバウハ ウスの話をし、<Part27>で、ピエト・モンドリアンの「ニュ−・リアリズム」 論を紹介した。 今回はモンドリアンの盟友で新興写真運動の闘士の一人でもあったラズロ・モホリ・ ナギ−を紹介し、彼のいう写真的表現の特質について簡略にふれておきたい。こうした 人々は、時代の先端を行った変革者、何を言い、それがどうなったか、文化史として一 応知っておくのも悪くない。 戦争というものは、科学の発達を促すとともに芸術の世界にも大きな変革をもたらす。 西欧社会では、以前は王冠と教会と資本という三つのものが民衆の運命のみならず、あら ゆる視覚芸術の方向をも決定していたものが、1918年、第一次世界大戦の終結とともに それらが崩壊し否定し去られた時、若い世代の芸術家たちの心ある者は、新しい原理を生み 出すような新たな視覚的表象を見いだすことこそ自分たちの天命だと覚悟したという。 モホリ・ナギ−もその一人であった。彼は、1895年ハンガリヤ北部の片田舎に生まれ、バ ウハウスの教授として1920年ベルリンに定住するようになる以前、すでにカンバス上或はコ ラ−ジュの画面に、形態と色彩のもつ表現力の価値を明らかにしていた画家であったが、人 間世界の創造に大きな力を持つ決め手である光線に非常な関心を示し、それが濃淡の諧調と 陰影をおりなす世界に興味を持ち、その解決を求めて画家から写真家に転向した。 彼はそこで友人の画家マン・レイが偶然に開発したフォトグラムに情熱を傾け、さらにま たフォトモンタ−ジュも制作した。それは、日常見慣れたものの映像を集め、意表にでるよ うな特異な配置を行って構成したものや典型的なニュ−ス種をよせあつめて張り合せ、文明 への痛烈な風刺を表そうとしたものであった。 やがて彼はナチの追放に合い、アメリカに渡って、シカゴのインスティテュ−ト・オブ・ デザインに主任教授として迎えられたが、生涯を通じての彼の思考と行動は、抽象絵画、彫 刻、工芸、建築、写真、映画と多方面にわたる新造形運動の発展に大きな影響を与えた優れ た啓蒙家であった。 日本では、真摯な教育者として印象に残った方に金丸重嶺氏がある。先生は新興写真の研 究、写真芸術に造詣が深く、社会活動も広範でブラッサイ、マン・レイ、ロバ−ト・キャパ などと親交のあった日本大学学長で、その当時日本広告写真家協会の会長でもあったことか ら、雑談のうちに何かと個人的な示唆をいただいたが、先生がア−ト志向の強かったぼくの 性格をみて、特に原点として推奨した作家がモホリ・ナギ−であった。 「アトリエ No, 321 写真と絵画(1953)」に、次のような金丸氏の記述が見られた。 金丸氏は、「写真のメカニズムの進展が単に機械的所産としてばかりでなく、それを人間 の感情表現の上において、空間的時間的に征服された時、写真はまたさらに新たに資格を獲 得し、常に表現を新しい世界に押し進めて行くだろう。 そうした過程は、芸術とメカニズムの知的な同化が新しい環境を生んで、外的と内的なつ ながりの中にあって、写真家がいつも受動的な立場にあることは予測できない」と言われ、 モホリ・ナギ−の造形理論の集大成といえる著書、『ヴィジョン・イン・モ−ション』の中 から、以下のような部分を紹介している。 (文章は直訳的で読みづらいが、そのまま記載する)
「芸術家は自分の道具の使用において 能力的に、あるレベルに達するとその手 段の範囲内で自由に表現の新しい分野を 探究して行く。そして手段についての問 題が進むと、創造的なエネルギ−が自由 になった表現の問題に直接集中して行く ことができる。 そこで問題は、意識的または潜在的の どちらでもよいが、これらの背後にある 感情の力の存在によって決定される。」 また、「これらの感情的な力を表現する ためのインスピレ−ションは、個性の中 に蓄積されている経験、教養の中から生 まれてくる。そして手段の選択は芸術家 自身の中にあり、芸術家はその表現を自 分の用いる手段の中から芸術的な統一を 導き出す能力を持たねばならぬ。そのよ うなことによって、写真は潜在意識的な 記録(秘められた心の中にあるリアリテ ィ−)に発展することができる。」 「写真はその初期から正確な観察に役 立ち直接に現実性をあらわすことで、科 学と理論に貢献した時代の理想的な道具 として発達したものであるから、これは 一見逆説のようにも見える。しかし、止 まるところのない芸術の世界は、常に表 現の領域を押し進めてゆくものである。 そのため芸術の精神の中に進む芸術家の 批判は、逆説を逆説たらしめないところ に、新しい一つの方向を発見してゆくも のである。」
「ヴィジョン・イン・モ−ション」 ラズロ・モホリ・ナギ−著
「そして新しい方向は、合理的な推論のみによって基礎づけられた現実的な<平面さ>や <単純さ>に反対し、より心理的な時空の領域に向かって進展していることを示唆し、新し いメカニズムによる視覚をもって、常套的なものや、予期されないものとの融合、組み合わ せの中に、<チャンス問題>とか<偶然の発見>というものを有意義な結果にすることによ った作家の表現的内容を拡大することを試みるべきだ。」という。 また、ナギ−はその著『マンレイ・フォトグラフィ・フィルム』のなかで次のようにも述 べている。「写真家は時代の眼であるのみでなく、良心でもある。その本領は過去の絵画の 伝統を研究して、どこに自らの任務の特異性が存在するかを知り、科学や技術を視覚の具と してその機能を最高度に生かして思うままに駆使し、また視覚的知識への一般的要求をみた すものとしてよりは、これを指揮する能力のある鋭い感覚と知識を備えた思索する人間とし て、真の写真家は現代の普遍像となるべきである。」といっている。 ナギ−の言葉は本筋を述べたものだが、具体的な表現の諸問題、人間の眼とカメラの眼 絵画的法則への反抗、カメラの眼を肯定する思想的な裏付けなど数多い問題ついては、 今後折りにふれ述べてゆくことにする。
とにかく、ぼくは写真家の眼で、油絵や水彩、リトグラフ、シルク・スクリ−ン、
イラストなど描いている現場を見過ぎてきた。瑛九やその仲間の多くの絵描きたち
の生の絵具による原画の生の色彩と写真というカメラのレンズを通し、フィルムに
定着し、カラ−印画紙に表現された色彩とでは、当然のことながら色その物のリア
リティがまったく違うのだ。
(絵を、写真に撮って印刷したものとの比較ではない)
当然、僕たち写真家は、写真科学の3大特性である物理的な精密描写や瞬間の固定、化学
的な感光材料によるグラデ−ションの表現(材質・肌理)を適材適所にフル活動をさせ、視
覚的に密度をあげた表現で対抗することになる。
しかし、ぼくは色光の加色混合やカラ−エマルジョンを知るにつれて、カラ−写真におけ
る表現は、新しい純粋な化学的色彩の中に、その視覚を創造してゆくことにも一つの方向が
あるのではと思うようになった。例えばカラ−エマルジョンやメカニズムの完全な可能性が
組み合わされば早い速度で動く色の光や色のあるシャド−を作り出すこともできるだろう。
また、自然界にある幻想を創造するばかりでなく、色のついた光によってさまざまな色光
が混合し、その反射や透過、重複によって新しい感覚を創造することも出来る。
これら色光については、ぼくは<写真特殊表現>の一環として、1960年から実験を始
め、いくらかの成果を得たが、その展開はますます果てしない。
今回からは、それらを「玉井瑞夫インタ−ネット写真展」に掲載することにした。
こうした作品は、一般の写真誌などで見られることは少なく、最初は多少理解しがたいか
も知れないが、いわゆるカラ−写真というジャンルにとらわれず、ひとつの表現として絵や
音楽を見聞きするように気楽に接してもらえば、そのうちに存在理由も理解されるようにな
るだろう。
解説はあまり技術の細かい話では退屈すると思われるので、当分は大ざっぱなよもやま話
になるかも知れない。つまり、こんな写真をやろうという人は少なく、制作プロセスの中で
の作者のざっくばらんな心理的な動きなどの方が、一般の撮影でも何かの参考になるかもし
れないと思うからだ。
ところで、こうした類の作品は、解説を読んでから鑑賞しては、本末転倒になる。
ある有名な音楽家が、「あなたの音楽にはどういう意味があるのですか」と聞かれた時、
「鳥が鳴いているのを聴いて、意味を聞こうとした人がありますか」と答えたという話があ
る。作品は視覚を通して体で感じるもの。本末転倒を続けていると視覚も鍛えられない。
殊に色彩やバランスの機微は、理屈でなく、視覚を通じて体で体得するより方法がない。
ぼくの解説は、作品を創るときのちょっとした心理的、技術的な参考に過ぎない。
本末転倒といえば、ぼくの本業が<写真特殊表現>の分野であったために、今後はかなり
変わった作品が掲載されると思うが、すぐそれに類するものを勧めるわけではない。また、
写真や造形の基礎を身につけなければ、すぐできる分野でもない。
それは形、技術の分野だけの話ではなく、やや写真を離れる部分もあるだけに他の文化、
類似のアートも理解しての表現が伴わなければ通用しない。近頃は写真家の中に外国語をし
ゃべれるというだけで、自国、日本の文化、色彩の変遷もおぼろげな自称国際人が現れ、外
国での本物の国際人とはまったく歩調があわぬといったことと同様になる。
もちろん、写真の本筋を志し、あわせて特殊表現への関心を持ち始めた向きには、非力な
がらぼくの体験をアドバイスしよう。
ぼくが本業とした広告宣伝の世界では、絶えずかなり個性あるユニ−クな創作的作品が
要求された。今回はポスタ−・カレンダ−・表紙用などに創られたものの中から比較的
手数がかからず、おだやかな作品を選んだ結果がたまたま植物の各種表現になった。
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|