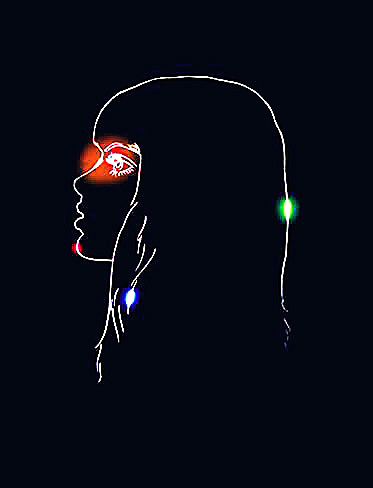< ゲーテは色彩学者でもあった >
ぼくの写真家としての特色は、色彩による写真特殊表現というのが、写真界
での通り相場だが、このところはまだ一般的な写真の入口での話が続いていた。
この辺から徐々に本筋に入ることにする。
さて、色彩を物理理論だけでなく、幅を広げて文化史的にも眺めると、ゲ−テの色彩論の
意義を再評価することになる。ぼくが学生時代には、ゲ−テは「ファウスト」や「若きヴェ
ルテルの悩み」などが必読書といわれ、写真家になるまでは、ドイツの詩人、作家というこ
としか知らず、彼が自然科学者、政治家であり、色彩学、形態学をはじめとする膨大な自然
研究をしてきたもっと幅広い、「ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲ−テ」であったとは
知らなかった。
|