 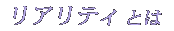 
前回は、フォルムとその周辺についての概念のような話をした。今回はもう少し
奥深いリアリティ、リアリズム論といったことについてのぼくの体験の一部を、
いくらかの参考になればと思い取り上げた。
今、ここに古ぼけたガリ版刷りの、わずか18ペ−ジの小冊子があり、それを紹介する。
ぼくは関西から上京して、写真誌の編集屋になった26歳当時、丹平の延長で編集者とい
うよりは作家といった意識のほうが強く、だれかれの区別なく怪しげな造型論を吹っかけて
迷惑がられていたが、そんなぼくをまともに取り合ってくれたのが前衛画家の瑛九だった。
啓蒙家の瑛九のところには、レベルの高い瑛九の芸術は、まだよくわからないが、とにか
く彼の人間的魅力にとりつかれた連中、まだ若かった画家や写真家の卵、デザイナ−、編集
者、バレリ−ナなどが絶えずやって来ていた。
やがて、彼らは封建的、権威主義に凝り固まった日本の既成画壇に挑戦する「デモクラ−
ト」という団体をつくったが、彼らは非常に研究熱心で、当時まだ入手困難な海外の造型に
関する文献を翻訳して「デモクラ−ト叢書」という小冊子をつくって、メンバ−に配布して
いた。ここに紹介するその中の一冊は、ぼくの宝物ともいえるもので、中塚、一之瀬、アイ
オ−君の3人で翻訳、編集し、デモクラ−トのみんなで翻訳を検討し合った労作である。
タイトルは、『リアリティの真の視覚に向かって』(モンドリアン自伝)とある。
(1942年、ニュ−ヨ−ク、バレンタインギャラリ−における最初の個展に際して
出版された英文より)
緒 言
文化というものは、リアリティの表現が変化しうるものであるという相対的な意
識を生み出す。この意識が明確になると、一つの反逆が起こる。すなわちリアリテ
ィのその表現からの解放が始まる。次にその制約が破壊される。直覚的能力の文化
が勝利を占める。恒久的リアリティの一層明確な理解が可能となる。
そして・・・新しいリアリズムが出現する・・・・。 ( A New realism )
< ピエト・モンドリアン >
ぼくたちは、この緒言とこれから派生する問題を3ケ月も討論し合った。
この緒言を読んで、はじめは理解しにくい人もあるかも知れない。しかし、そのうちに自然
とわかるようになるだろう。
ぼくは年月と共に体にしみるように入ってきた。
モンドリアンは、造型芸術の論理的な発展を『ネオ・プラスティシズム』と名づけ、現代
の新しい建築、ポスタ−、広告、レイアウト、インダストリアル・デザイン、そして写真の
分野にも大きな影響を与えたが、そのころの絵画や彫刻はほとんど影響を受けなかった。そ
れらの分野は伝統的な表現方式により多く束縛されていたからである。
モンドリアンの造型論はすばらしく、ぼくは、彼の言葉から多くの示唆を得たが、そ
れを詳述していると今回の話が進まないので、要点をはさみながら先へ進む。
|



