「 犬と靴と 」
ぼくは、大阪から上京し、写真雑誌の編
集者になったが、生涯編集屋をやる意志は
なく、カメラをいつもぶら下げていた。
編集屋は超多忙でぼくの好きな風景を撮
りに行く暇はなかった。
住居はまだ敗戦の匂いがただよう場末の
ような池袋で、手近かな路地で遊ぶ子供や
犬などを気ままに撮っていた。
しかし、開放的なスナップをと思いなが
ら大阪で学んだ身にしみた構成主義は、フ
ァインダ−を覗いたその瞬間に、がっちり
と身動きできないような写真、縦横十文字
の構成になってしまうことも多かった。
これも一長一短、功罪相半で、この犬の
場合も丸まった犬のフォルムと向こうに見
える靴の構成には玉井流がすぎてゆとりに
欠けるものになっている。
|
|
「 野犬 」
前回、ぼくは石元泰博氏を造形の確かな
写真家として紹介した。
その彼がニュ−バウハウスで受けた造形
教育の影響は確かに大きく、そこからの脱
皮が問題だといい、最近まで撮っていたシ
リ−ズ「人の流れ」はカメラを腹のあたり
に構え、ノ−ファインダ−で歩きながらシ
ャッタ−を切る手法で撮っていた。
ぼくもまったく同様で、カルチェ・ブレ
ッソンの「決定的瞬間」に刺激され、自分
の殻を破るつもりで、膝の高さ、犬の目で
見た池袋をノ−ファインダ−で撮っていた
ことがある。これはその一枚である。
こうした試みは、自分のフレ−ムが決ま
り過ぎ、その枠から脱出するするキッカケ
をつかむため、やってみることもいい。
ぼくにはこの手法がある程度役立った。
|
|
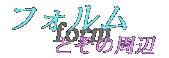 (1)
(1) 
(1)
