part.24 
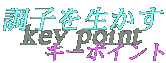
< コントロールをなぜ行うか >
今回、掲載した作品は47年前に撮影されたもので、鑑賞と技術解説をかねたもの
である。写真におけるグラデ−ションのひとつの原点として参考にされたい。
ぼくが写真をはじめたころは、モノクロ−ムだけでカラ−写真はなかった。
自然界のすべての色彩をニュ−トラルな白と黒とその間の濃淡の諧調(グラデ−ション)
だけで見せるのは、抽象的な表現をするモノクロ−ム写真の格別の魅力である。
当時、「写真をやっている」ということは、アマチュアでも自分で現像、引き伸ばしもし
ているということを意味し、それが普通であった。
1960年代以降に写真をはじめた若者(弟子や写真学生)たちは、カラ−での入門がほ
とんどで、写真の基礎を理解させるために、あらためてモノクロ−ムを写させることをした
が、ぼくたちモノクロ育ちの常識が通用せず、フィルタ−なるものも知らず、時折不思議な
質問をするのであきれることもあった。
モノクロ−ムの撮影や引き伸ばしの参考書を開けば、フィルタ−の使用や暗室作業での焼
き込み、覆い焼きなどという言葉がでてくるだろう。それらはぼくたちが当然のこととして
やってきたコントロ−ルだが、彼らにはその意味がなかなか分からぬようであった。
「写真は、真を写す」ということだから、引き伸ばしの作業中に、まるで墨絵でも描くよ
うに白黒の濃淡を変えてもいいものだろうか、写真の冒涜ではなかろうかなどという。
これは、フィルムの化学的な性質を知らず、頭からフィルムは正しいと思いこんでいる錯
覚からである。
モノクロ−ムのフィルムは、画像を感光するベ−スに銀塩を使っているが、銀塩は肉眼で
は見えない紫外線に一番よく感じる性質がある。人間の眼とは違うのだ。もちろんフィルム
にはパンクロマティック(全整色性)と書かれているが、基本的なモノクロの性質は変わら
ない。
晴天の空を見渡すと、水平線の近くは薄いブル−で中天にいたるほど濃いブル−である。
これをモノクロ−ムのフィルムで表現すると、紫外線が一番よく感じてしまうので、見た目
よりもずっと白っぽい空に写ることになる。そこで紫外線の感光性を抑える黄色フィルタ−
をつけて写せば、青空の濃淡をやや薄いグレ−から濃いグレ−に置き換えた空の実感が再現
できることになる。
同様に、いくら整色性があるといっても、中くらいの明度の黄色も青色もモノクロでは、
中くらいのグレ−に写るだけだから、肉眼にはより強く感じる彩度の高い黄色の部分を実感
通りにしたければ、引き伸ばし時に覆い焼きで更に明るいグレ−に調整するのは、作者とし
ては当然のことである。
カラ−フィルムでも種類によっては同様なことがある。ぼくはシャネルの仕事も長くして
いたが、香水の黄色と一緒に男性用の微妙な淡い黄緑色のトワレを写すと実感通りには写ら
ずカラ−修正をするのが通例であり、また宝石のエメラルドなどはグリ−ンの感色性も不足
するので、その部分だけ照明を明るくするか露出を長くするなどもある。
さらに、衣服での化学染料による偏光のあるものは、肉眼とは相当異なった色彩に、フィ
ルムが表現することもよく経験した。
要するに感光材料は完全ではなく、自分の感性を中心にコントロ−ルするのは、感材まか
せフィルムまかせでは納得できない写真家の良心であろう。
ここに紹介した「夜明け前」という作品は、写真誌の口絵として発表したもので、モノク
ロ写真の感色性と肉眼による実感との差を調整する問題、つまりプリントにおける<コント
ロ−ルはなぜ必要か>という作品の質を上げる適例として、本文に実技も述べられている。
編集長は、「機械的なフィルムの感色性と作者の実感との間をどのようにコントロ−ルし
たのか、問題の核心を書いて欲しい」ということで、その当時にぼくが書いた解説文をその
まま、写真評論家の渡辺好章氏の「鑑賞」と共に掲載した。
こういう問題を解説した記事は当時としては珍しく、その後もなかったので紹介した。
|
|
「 夜明け前 」 玉井瑞夫 (真鶴にて) 1953
|
 「 夜明け前 」 「 夜明け前 」
自然は無限の感情を持っている。季節により、時間により、また天候によって万化する。
夜明け前の海は一瞬、妖しいい表情をする。濡れた砂浜は夜であり、波頭は朝であり、空は
朝と夜の中間である。
平凡な海景だが、珍しい表情をとらえて、非凡な作品にしている。夜明け前から海浜に立
った情熱ときわどい明暗のバランスを表現し得た技術を買うことができる。
熟睡した朝のさわやかな気分と、相通ずる透明な空気が画面いっぱいに流れ、砂浜は冷た
く暗く、返す波は油のように静かに、波頭は朝の元気、雲はまだ眠りから覚めない。画調の
統一に仕上げ技術を駆使している様子がうかがわれるが、これが成功のカギであったろう。
(写真サロン 1953年) [渡辺好章]
|
|
 |
<制作ノート>
 夜明け前 夜明け前  2月末日。5時頃、未明の海を写した
いと思ってまだ真っ暗い海岸に立つ。
曇天のせいもあってか、空と海の境も
見極めがたい。眼が闇に慣れるにつれて
海の呼吸のような波の砕ける響きの合間
に波頭だけが仄白く見える。
なおも目を凝らせて見ていると、波の
山が崩れ始めるあたりから波打ち際まで
の間に水蒸気のようなものが立ちこめて
いるのに気がついた。海水より大気の方 夜明け前 原画
が冷たいためであろう。
予想通り妖しいまでに美しい未明の海だが、この明るさではF1 ,4 でも写らない。
何百倍も感度の良いフィルムが欲しいと思った。カメラはロ−ライフレックス、残念だが
F3.5開放で、25分の1 秒が切れるまで待つ。波までかなりの距離があるのだが、これが
波を正面から写しとめる最低限度と思う。やっと25分の1 秒が切れる頃になると、もう未明
の海の感じはかなり失せてきたが、後処理を考えながら写してみた。
ギリギリの露出でネガは相当薄い。このネガは柔らかすぎるので、プリントでは夜明け前
の暗さまで暗くすると波のハイライトがくすぶるばかりで、ネムイ調子になる。
これを硬調紙にプリントすると、波の山から海岸線までの間は大体実感に近いものになつ
たが、空は肉眼に感じた以上に明るく、砂浜は暗すぎて真っ黒につぶれてしまい、実感には
程遠い調子になる。
波の白さは、夜明け前の暗さでは真昼に比べるとハ−フ・ト−ン位かもしれないが、あた
りの薄暗いこの時刻では、実感上は砕ける波頭はハイライトに感じるものである。
また、われわれがゆっくり時間をかけてものを見るときは、明暗差の大きい暗い室内と戸
外を同時に見る場合と同じく、天地の明暗差の大きい場合、肉眼の視覚が狭いことから、目
の玉を動かしながら、明るい天部は自動的に目の絞り(瞳孔)を小さくし、暗い砂浜は反対
に目の絞りを大きくして見る印象の総合されたものがイメ−ジとして頭に残る。
これは、人間の視覚がもつ明順応、暗順応という状態である。
しかし、カメラはまったく機械的に写しとるだけだからこの印象との差が出る。この例の
場合は夜明け前という条件で長く眺めていたために、その差をより多く感じたように思う。
人によっては異論もあろうが、私の実感に近づくよう、写真のメカニズムを出来るだけ尊
重しながらも引き伸ばしでは相当のコントロールを加えてみたのが口絵である。
波と手前の海を基準におきながら覆い焼きによって砂浜をやや明るくし、空は上に行くほ
ど焼度を多くかけて暗くしたものである。砂浜を明るくしたことは、海の冷たさが少し出て
きたように思え、低く垂れ込めた曇天の暗い空は夜明け前の暗さを感じさせたように思う。
しかし、このままでは空の中央の雲がやや白すぎて波の力を弱めるので、この部分だけな
お少し焼き込むなどのコントロ−ルをした。
とにかく、調子のバランスがむつかしく、1ダ−スもロ−キ−気味のプリントをしてやっ
と仕上がったのがこの1枚であった。
いわば調子で見せる写真だが、印刷でどの程度出せるか。
2月末日。5時頃、未明の海を写した
いと思ってまだ真っ暗い海岸に立つ。
曇天のせいもあってか、空と海の境も
見極めがたい。眼が闇に慣れるにつれて
海の呼吸のような波の砕ける響きの合間
に波頭だけが仄白く見える。
なおも目を凝らせて見ていると、波の
山が崩れ始めるあたりから波打ち際まで
の間に水蒸気のようなものが立ちこめて
いるのに気がついた。海水より大気の方 夜明け前 原画
が冷たいためであろう。
予想通り妖しいまでに美しい未明の海だが、この明るさではF1 ,4 でも写らない。
何百倍も感度の良いフィルムが欲しいと思った。カメラはロ−ライフレックス、残念だが
F3.5開放で、25分の1 秒が切れるまで待つ。波までかなりの距離があるのだが、これが
波を正面から写しとめる最低限度と思う。やっと25分の1 秒が切れる頃になると、もう未明
の海の感じはかなり失せてきたが、後処理を考えながら写してみた。
ギリギリの露出でネガは相当薄い。このネガは柔らかすぎるので、プリントでは夜明け前
の暗さまで暗くすると波のハイライトがくすぶるばかりで、ネムイ調子になる。
これを硬調紙にプリントすると、波の山から海岸線までの間は大体実感に近いものになつ
たが、空は肉眼に感じた以上に明るく、砂浜は暗すぎて真っ黒につぶれてしまい、実感には
程遠い調子になる。
波の白さは、夜明け前の暗さでは真昼に比べるとハ−フ・ト−ン位かもしれないが、あた
りの薄暗いこの時刻では、実感上は砕ける波頭はハイライトに感じるものである。
また、われわれがゆっくり時間をかけてものを見るときは、明暗差の大きい暗い室内と戸
外を同時に見る場合と同じく、天地の明暗差の大きい場合、肉眼の視覚が狭いことから、目
の玉を動かしながら、明るい天部は自動的に目の絞り(瞳孔)を小さくし、暗い砂浜は反対
に目の絞りを大きくして見る印象の総合されたものがイメ−ジとして頭に残る。
これは、人間の視覚がもつ明順応、暗順応という状態である。
しかし、カメラはまったく機械的に写しとるだけだからこの印象との差が出る。この例の
場合は夜明け前という条件で長く眺めていたために、その差をより多く感じたように思う。
人によっては異論もあろうが、私の実感に近づくよう、写真のメカニズムを出来るだけ尊
重しながらも引き伸ばしでは相当のコントロールを加えてみたのが口絵である。
波と手前の海を基準におきながら覆い焼きによって砂浜をやや明るくし、空は上に行くほ
ど焼度を多くかけて暗くしたものである。砂浜を明るくしたことは、海の冷たさが少し出て
きたように思え、低く垂れ込めた曇天の暗い空は夜明け前の暗さを感じさせたように思う。
しかし、このままでは空の中央の雲がやや白すぎて波の力を弱めるので、この部分だけな
お少し焼き込むなどのコントロ−ルをした。
とにかく、調子のバランスがむつかしく、1ダ−スもロ−キ−気味のプリントをしてやっ
と仕上がったのがこの1枚であった。
いわば調子で見せる写真だが、印刷でどの程度出せるか。
|

|
「 真夏の海 」 玉井瑞夫 (真鶴にて) 1953
「 真夏の海 」
これも同じ場所での季節を変えての撮影である。前者は静的な、後者は動的な一対の風景
作品としての試作である。(これは未発表の作品である)
「夜明け前」は冬の薄暗い夜明け、雲と平凡な海岸だけしかない写真でも、諧調の厳密な
コントロ−ルによっては、ひと味違った作品として成立するということだった。
これと対照的に、「真夏の海」は夏雲と強風で波頭が白くしぶかれ、流れるような海を、
特殊な感材とフィルタ−効果で、平凡になりやすい風景を象徴的な作品として見せようとし
たものである。
このモノクロ作品は赤外フィルムによる撮影だが、フィルムベ−スはやはり銀塩でそれに
赤外の乳剤を乗せてあるので、そのままで写すと青空は明るく普通のモノクロ写真になる。
そのために赤外効果を見せるには、紫外線を完全にカットする濃い赤フィルタ−をつけて
写すことになるが、快晴の空は真っ黒に、雲はことさら真っ白に表現される。
この闇のような黒さは、濃い黄色フィルタ−やオレンジフィルタ−での青空を思わせる濃
いグレ−の空とは異なり、もうひとつ次元の違った表現、虚無的な宇宙の奥を思わせるよう
で、これもすばらしい。
いずれにしても、この2点の作品は、写真家に成り立てのころ、ぼくもまだ若く,かなり
のへそ曲がりから友人たちの前で、「どんな平凡な風景でも、作品として表現して見せる」
などと広言したことから、自らに難しく微妙なト−ン・バランスという課題を与えて実験し
たものである。
|

|
< グラデーション あれこれ >
その頃、ぼくは製版屋なみの濃度計を買い込んで、モノクロ−ムの濃淡を階段に表したコ
ダックのチャ−トを傍らにおいて、撮影した透光でみるネガと反射光でみるプリントを測定
しながら完全なト−ン表現を目指した実験をやっていた。
その主なテ−マはグラデ−ションの在り方で、「等差級数的なものと等比級数なものでは
視覚的・感情的にどんな違いがあるか、またその接点や突然変異的なバランスの及ぼす影響
はどんなものであろうか。」などにはじまって、「音楽における短調(主和音が短三和音)
が暗い、さびしい響きを持ち、長調(主和音が長三和音)は一般に明るい響きをもつが、こ
れをモノト−ンの写真の諧調に直すとどういうことになるか。」などであったが、こんなこ
とは、どこの学校でも教えておらず、暗中模索であった。
時に脱線して、ざっくばらんの仲間に、「平安貴族の美意識には、「あわれ」「おかし」
という対照的な2つのタイプがある。紫式部の源氏物語の「あわれ」は湿っぽくて内向的、
清少納言の枕草子の「おかし」は乾いて快活で外向的だとぼくは思う。これを諧調でいえば
−−−−。君はどう思うか。」と聞いたら、以来「玉井は、もう重症のグラデ−ション病に
かかっている」といわれ、後に特殊表現に凝ってカラ−の実験をはじめたときには、ついに
「色気違い」ということにされてしまった。
余談になったが、つまりぼくの実験の究極は、この2枚の作品でも画面に1インチ角の遊
びも許さず、完璧なト−ン・バランスをもった印画をつくろうとしたことである。
また、こうした風景の空と海の構成バランスはほとんどの場合いずれかを主体にした7:
3であったことから、ぼくは意図的に水平線を真ん中近くにおいての新鮮なバランスをとる
ことも試みようとした。
モノト−ンのモノクロ−ム写真での基本的なバランスの取り方を覚えると、より複雑なカ
ラ−バランスでの会得も早い。こうした問題は、また項をあらためて解説するつもりだ。
結果は、格別に際立った材料もない海でもはかり知れない魅力をもつ情景となる造形の条
件と、自分なりに感じた実感を何とか表現できたものとして、いまだに自分ではかなりお気
に入りの作品である。
ただ、どこがどうして良いのだと聞かれると返答に窮するという自分の深層心理をみるよ
うな、自分好みの音を聴いているような漠然とした作品でもある。
どういうわけかぼくは、こうした漠然として何となく気にかかる作品からは、割合い抽象
的な音や音楽の一節を聴くような気分になる。それらは年月を経ても変わらぬクラシックで
あったり、つい先頃聴いた癒しの音楽だったりする。
それは自分の作品ばかりでなく、ぼくが感銘を受け脳裏に残る写真や絵を見た時も同様で
音は折々の心境で変わることもある。
久しぶりに見た「夜明け前」からは、能の囃しのようなリズムからはじまり、ぼくの好き
なアヴェマリアの各曲を歌うテナ−のアンドレア・ボッチェリ−の声が聞こえた。
また「真夏の海」はショパンの「革命のエチュ−ド」が、つづいてこの曲に共通点のある
加古隆のピアノが聞こえてくるといった具合で、折々に音が浮かびイメ−ジは増幅する。
ナチス侵略時代のテレビ映像のバック・ミュ−ジックによく使われている「革命のエチュ
−ド」が浮かんだのは、「真夏の海」の何か切迫した不安を思わせる動的な雲と海の流れに
共通性を感じるのかもしれない。
話は変わるが、ここで浮世絵版画の風景作品を思い出してもらいたい。
浮世絵の多くの風景をよく見ると、上部の空の表現に2〜3センチメ−トルほどの幅で、
重ね刷りで濃淡をつけていあるのがわかるだろう。写真でいえば、水平線の薄いグレ−から
中天のかなり濃いグレ−までの濃淡を、浮世絵ではさらに圧縮したような表現である。
(Part 21 に掲載の浮世絵、北斎の「凱風快晴」その他 参照)
すでに、江戸時代の浮世絵師がわずかなスペ−スでのこうした工夫で、画面全体の密度を
上げていたことに気づいたのは、50年も前のことである。仲間の画家、池田満寿夫は浮世
絵からセクシャルな筆致をまなび、ぼくは空間表現の極意を学んだ。
こうした見事な心にくいばかりの空間表現に驚き感心して以来、ぼくはこれを意図的に写
真表現で自分流に真似てきたが、モノクロ−ムの風景写真で、多くの写真家が空の部分を焼
き込んでグラデ−ションを強調するのは、今日では全く当たり前のことになった。
|

|
< モノクロ よもやま話 >
47年前の問題作を例にあげて解説を書いていると、その頃の第一線の写真家の名作とい
われたモノクロ作品がその人の風貌と共に次々と浮かんできた。
それらは瑞々しく、その折々の話も作品も新鮮で、それらは世紀が変つた今日でも高い評
価をうけているもので、ぼくは少々よもやま話を書く気になった。
当時のぼくは、初め写真雑誌の編集者として、また後には写真家として、土門拳、木村伊
兵衛、浜谷浩、福田勝治氏などの大先輩にはじまり、林忠彦、秋山庄太郎、杉山吉良、吉岡
専造、三木淳氏などの兄貴分、同輩には稲村隆正、石井彰、船山克、渡部雄吉氏など、その
他数十名の方々に親しくいていただいたが、これらの方々のオリジナルのゼラチン・シルバ
−プリントは、作者が諧調のどの部分を重視するかによって千差版別だが、写真家の個性が
出るために、裏面のサインを見なくても誰の作品かはおおよそ見当がついた。
各人各様の個性と訴求内容によってそのプリントはハイキ−、ロ−キ−さまざまで、土門
氏は単刀直入で力強く、反対に木村氏はソフトで、女性写真など印画のト−ンにも色気が漂
っていた。特写に随行してネガを見せてもらったこともあったが、露出の与え方も異なり、
ネガ作りにまで個性があるというのが、第一線の写真家たちであった。外国の作家ではユ−
ジン・スミスのシャド−部のフルスケ−ルを使ったすばらしい作品など印象に残る。
先輩各写真家の特質やぼくたちの後に続く人々で新しいヴィジョンを展開し、ぼくを刺激
してくれた若い写真家については、またチャンスをみて話したいが、この頃からぼくが特に
注目してきたのは、造形に強い石元泰博氏のモノクロ作品であった。
ぼくが石元氏に初めて会ったのは、彼がアメリカから帰ってきた直後の初夏の銀座であっ
た。喫茶店で写真評論家の渡辺好章氏と話をしていたら、そこへ渡辺氏を訪ねてきた。
ライカをぶら下げて入ってきた彼は、いきなり「戸外の撮影で8×10のフィルムが、露
出中に動いてピンボケで困る。8×10判の乾板が欲しい」といった話をはじめた。
ぼくは、「日中の戸外で、いくら暑くて湿気が多い日本でもフィルムが露光の間に動くほ
ど長時間かけて写す写真があるものか」と不審に思ったが、これは彼が「桂離宮」の撮影を
始めたばかりで、庭の石や苔を最小絞りで真下に向けた俯瞰撮影をする時のことだった。
ぼくは、その後完成した「桂離宮」の写真集を見て、彼の知的で明晰な造形美に驚いた。
それ以後のぼくは、造形の原形サンプルのように「桂離宮」を誰にも薦めた。
彼は1919年、ドイツに生まれた前衛的な造形学校バウハウスの流れをくむ、シカゴの
通称ニュ−バウハウスの造形教育を身につけた日本では珍しいタイプの写真家として注目さ
れてきたが、特にモノクロ−ムで抜群の構成と静謐な諧調を見せた作品を創る彼の言葉は、
瑛九の造形論の洗礼を受けたぼくが考え実行してきたこととほぼ同様で、その原理、基本は
今日も変わらない。
フジフィルムの「Pro VALUE」という機関紙のごく最近号( 2001年 9月号) の座
談会にある石元氏の発言の一部を、以下に紹介しておこう。
○僕が黒白写真にひかれるのは、現実を抽象化するおもしろさがあるからだ。抽象
化することによって、自分の主張をストレ−トに表現することができる。
その点、カラ−写真は情報量が多過ぎて、色に邪魔されて言いたいことが伝わり
切らないきらいがある。
○写真は確かに現実を写すものだが、優れた写真家は現実を越えた抽象的なものを
表現できると、僕は思っている。
○被写体の向こう側に、写真の普遍性が見えてくる。写真も写っている被写体を越
えて、普遍的なものに迫ってゆかないといけない。
○僕のこれまでを振り返って、作品として残っているのは、プライベ−トに撮影し
てきたものばかりだ。アマチュア的な純粋さで、なにものにも束縛されず自分の
表現を確立してきたことが、今日につながっていると思っている。
○一歩踏み込んで撮るか、引いて全体像を見せるか、写真家は自分の主張とフレ−
ミングの関係を常に考えて置く必要がある。
○僕はニュ−バウハウスの教育を受けたせいで、物事を造形的に見る習慣がついて
いる。ファインダ−をのぞいた瞬間、無意識のうちに被写体をすべて関係づけ、
フレ−ミングしてしまうのだ。
それにはプラス面もあるが、マイナス面も少なくない。どうしても決まり過ぎた
構図になってしまうのだ。そこからの脱出が僕の課題だ。
○大切なことは自分の考えをしっかり持ち、自分の表現を確立することだ。そうで
なければ、自分を見失ってしまいかねない。流行を追ってばかりでは、時代に消
費され、使い捨てにされてしまうだけだ。
○写真のテ−マは、問題意識を持って自分の回りを見渡していると、自然に見えて
くるものだ。既成概念にとらわれず、自由な目と心で身の回りを見つめ直して見
ること。そうすれば新しいテ−マが見つかり、それに適した最善の表現方法も生
まれてくる。
彼の言っていることは、ぼくもずっと弟子たちに話してきたような話で、特に目新しいこ
とではないが具体的で分かり易い。ぼくが先に述べた先輩諸兄のほとんどはもう他界されて
いるが、この方たちが50年前、折々に言われたことや瑛九やその仲間の画家たちのいった
ことを総合すると、表現はやや変わっても内容のポイントは共通する。
ぼくが、「造形の原理は前漢時代、紀元前200年頃に完成され、以後は時代による粉飾
あるのみ」、「原理は時代に合う様式[粉飾]で生かされる」という、表現の原理・原則、
基本は、変わらないというのも同様である。
結論は、上記の意味を理解しながら、「各人各様の個性を生かした写真表現を試みる。」
ということにつきる。
現代の写真を含めての芸術は、いわゆる美しいといわれるものだけの追求ではない。
それはまたその作者が、如何に現実を見、いかに現実に懐疑し、夢み、喜び、悩み苦しん
だか。如何に生きたかを、昇華した表現(造形)で語りかけるものであろう。
そのことは、やがて共感する人々が心を開き、写真だけでなく文化を共有する場にな
り、より豊かな交流が始まるであろう。
ぼくはそんなことを願って、この講座を始めた。
|

|



「 夜明け前 」

