part.20 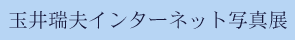
<<< 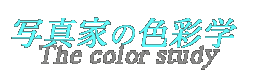 (3) (3)
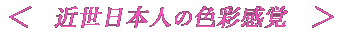 その1 その1
「色」ほど複雑なものはない。色は匂いや味や音や触感と共に、人間の基本的な五つ
の感覚、五感の一つだから、物理学や化学の知識だけでは簡単には割り切れない。
もうかなり前になるが、僕は写真批評家で能の笛にも堪能な渡辺好章氏に誘われて、観世
流家元の土用干しを拝見したことがある。加賀百万石・前田利家公の着用したものをはじめ
数々の重要文化財級の由緒ある衣装、能面が大量に掛けられ並べられていたが、練絹の厚み
の手ざわり、色合いの深さを味わい、ことに紋様のデザインは現代のデザインも顔負けする
くらい斬新かつ大胆なもので、その美しさに圧倒され、あきることがなかった。
そして、真近かに見たあの大胆な派手さ、鮮やかさが能の本舞台では、すべてがしっとり
と渋く、落ち着いて見える秘密が、平安の昔からある草木染めなど天然の染料にあることが
良く理解できた。
今回も前回に続き、「色彩の時代、時代による変遷」について話しておきたい。桃山時代
から江戸時代は非常に題材が豊富なこともあって、色彩の説明だけでなく、多少の作品解説
も加えることにした。
今回は掲載作品が多いので、インタ−ネット写真展の方は休会とした。
|
|
 金色に憧れた桃山時代 金色に憧れた桃山時代 
室町から一転して近世に入る。
あの戦国時代を経て桃山時代という豪華絢爛な文化を生み出した時代がやって来る。
この桃山時代から江戸時代の前期にかけて、日本人の感覚はもう一度古代の多色時代に立
ちかえったような状況を呈した。
桃山時代は短く終わったが、日本文化の気配を転換した。
乱世に終止符を打たれた人々は太平の世を久しぶりに迎え、生きのびたことを喜ぶとともに
現世享楽の様相を展開した。
桃山時代で目立つのは、金色に対するあこがれと執着であろう。この金の色は、前に奈良
時代の仏教文化でのべたように、色というよりはむしろ光り、燦然とかがやく仏の世界を象
徴するものであったが、桃山時代の金色に対する観念は仏の世界の色ではなくて、この現世
にある最も豪華な色、絢爛たる色というきわめて現実的なものであった。
この時代の絵画では、障壁画といわれるものが、武将の城や館のみならず、公家の邸宅も
寺院も、一般の町衆の屋敷にもゆきわたり、美々しく飾り立てられた。
この障壁画は金碧濃彩画つまり金箔を張りつめた金地の上に極彩色で描くというもので、
この様式が全盛を極めた。桃山画壇で最も多くの俊英を輩出させ一大王国つくったのは、漢
画系の狩野派で、安土城、聚楽台の障壁画に筆を振るい、その名声は他に並ぶものがなかっ
たという。
|
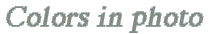
|

「唐獅子図」 狩野永徳
これは、豊臣秀吉が毛利軍と講和したとき、その記念として贈った陣屋屏風
といわれる。画面の天地だけでも225センチ・メ−トルという比類のない大
きさだが、これを大胆に描きこなした筆力もまた驚嘆に値する。
誇張もあり粗放とも見られる向きもないわけではないが、いかにも戦国の武
将たちの好みにふさわしい画面であったのだろう。
|
|
 狩野派の全盛期は 狩野派の全盛期は 
御用絵師、狩野永徳という画家によるこの様式は、狩野派だけでなく他の諸派の画家たち
にも模倣されて桃山から江戸時代の初期は、京も浪花も江戸、名古屋の町々にもこの金碧濃
彩画が氾濫した極めて華やかな時代であった。
今日、京都その他の寺院や城にのこっている、また屏風の形で伝わっている当時の障壁画
は、数百、数千分の一に過ぎないかも知れないが、往時の盛況を充分に示している。
例えば、狩野永徳が描いた御物の唐獅子図屏風の金地に極彩色の強烈で堂々たる画面をは
じめ、長谷川等伯その他の流派の紺碧の大花木画、その他数々の画家たちが腕を競った大画
面に、われわれは近世初期のあきれるばかりの色彩の氾濫をうかがい知ることができる。
これらは、戦国時代の覇者、織田信長、豊臣秀吉たちによって、その力や権勢、財力とい
ったものを誇示せんとしたデモンストレ−ションの意識に支えられて生み出された現象であ
った。そして、それは支配者だけでなく一般人も前の時代に比べて黄金の恩恵に浴した時代
であった。当時は金の産出額が非常に増加したこともあって、一般人も黄金が手のどどかな
いものではなくなった時代、日本の経済力の高度成長時代であったといえる。
ところで、障壁画を建築学的、写真的な見方からするとどういうことになるか。
おおざっぱに言って、書院造りの建物で、金屏風や金箔緊迫をはった障壁画は、それが金
持ちであり、かつ権威を表現したこともあるが、同時に天候の変化によって内部空間の暗闇
のなかに、ある種のきらめきをもった絵画が出現する一つの手段であった。ある瞬間、屏風
の一角がハイライトのように光る。それが障壁画の金を使った最大の理由であろう。
|
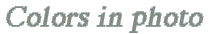
|
 |
 |
「風神雷神」 俵屋宗達
この屏風の前に立つ誰もが、しばし足を止めさせられる魅力と力強さをもっ
ている。宗達が費やした時空と情熱を肌で感じるような画面である。
宗達が人間的にも技術的にももっとも円熟したころの作品であろう。
|
|
|

「千羽鶴」(部分)
|

「夏秋草図」(部分)
|
「千羽鶴」(部分) 尾形光琳
鶴の描写は一見すると無造作だが、ほのかに匂う胡分の白い鶴とすこし黒ず
んだ渋い調子の銀の鶴とが金地に入り乱れて配置され、それらの対比は絶妙で
ある。光琳の絵には時折宗達の影響が見られるが、彼にとって宗達は良き師で
あり、また意識せずにはいられないライバルでもあったのであろう。
「夏秋草図」(部分) 酒井抱一
秋草の上をさっと吹き渡る風の音が、さわやかに聞こえてくるようである。
繊細な神経が草花の一つ一つにゆきわたり、抱一独自の自然の写生と理想化の
微妙な合致が見られる。
抱一は光琳を隔世の師と仰ぎ、光琳が宗達の「風神雷神」を模写した屏風の
裏にこれを描いている。
|
|
 宗達と光琳 宗達と光琳 
絵画で、金泥や銀泥を使って描く手法は、平安朝以来細々と続いていたが、この時代にな
って目ざましく復興した。俵屋宗達が本阿弥光悦と共に制作した金銀泥の色紙は、金銀泥の
輝きやむらむらの効果を最大限に活用したもので、他の国では見られない日本独自の芸術で
あるが、この時代にふさわしい、同時に極めて新しい色彩感覚を発揮したものといえよう。
宗達は、御用絵師として制約の大きかった狩野派とは違い、市井で扇屋を営む自由気楽な
町絵師であった。絵師は手本や師匠の作品を忠実に再現する。それが当時の常識だった。
ところが宗達は、構図も人物も、どこからか借用してくる。今なら盗作、盗用騒ぎになり
かねないところだが、それを独創的、斬新なアイディアで味つけし、一歩別の世界へ踏み出
す。普通ならまとまりがなくなるところだが、それを傑作にし仕上げてしまういう才能を持
っていたらしい。
宗達の構図には独特の味わいがある。宗達は扇屋という商売柄、扇面という末広がりの特
殊な画面形式では、四角い画面とはちがった描き方の工夫があったために、ことさら構成に
長け、後に大作を頼まれるようになった時、独自の斬新な絵が生まれたのであろう。
尾形光琳ははじめ狩野派に学んだが、宗達に傾倒、美麗な装飾的な画風を完成し、蒔絵に
も美しい光琳蒔絵を考案し、元禄文化の粋をつくりあげた人である。
宗達と光琳の違いは宗達が常に楽々と対象と一体になったのに対し、光琳は一方で対象の
客観的な把握につとめ、他方で造形化をはかるところにある。大胆な装飾画の大家として知
られる光琳は、反面において、我が国にあっては「写生帖」を残す最初の画家でもあった。
この2人は琳派の開祖といわれ、装飾芸術の新たな突破口になった。酒井抱一は光琳に傾
倒し、庶民的な独自のすばらしい装飾画を遺した人である。
|
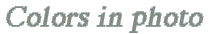
|
 |
 |
「草花模様段縫箔」
|
「金銀襴緞子等縫合胴服」
|
「草花模様段縫箔」(くさばなもようだんぬいはく)
桃山時代の小袖模様の代表的なものの一つである段模様で、これに一面四季
の花や短冊などを総縫いにした見事な能衣装である。
これは小袖の半身に、ニつの異なった模様キレを用いて作る半身替わりと同
じく、もとは数多くのキレをはぎ合わせて作ることにはじまったといわれ、こ
れは一つの模様構成の型になっていた。
「金銀襴緞子等縫合胴服」(きんぎんらんどんすとうぬいあわせどうふく)
上杉謙信が着用したといわれる。当時の舶来品である金欄や緞子を張り合わ
せた豪華なものである。そのデザインは、現代の抽象絵画を思わせる見事なも
のである。
|
|
 小袖・能衣装のすばらしさ 小袖・能衣装のすばらしさ 
こうした桃山時代の豪華絢爛主義は、絵ばかりでなく、染織や漆器や陶磁といった工芸の
世界でも同様であった。
小袖というのは、今の着物の古い名まえといったところ。いかに美しくとも生活に不便な
ものは実用化されないが、小袖は広い袖と開いた裾で、日本の湿度から逃れる通風のよい着
物である。また、洋式の石造りや煉瓦づくりの建物は材料の固さ、冷たさから座ることを許
さないが、木造建築での座る快感があることにも原因があるようだ。
当時の小袖には、男であることに気づかぬほどのあでやかな装いをしたものもあったとい
われたが、僕は初めて上野の博物館で豊臣秀吉の愛用したという小袖を見た時、とても男物
とは思えない色合い派手さに驚いた。緊急時には頭から被って避難すれば女性に間違われて
難を逃れることもといった話も納得した。
能楽は室町時代、足利義満の庇護を受けて、世阿弥は父の観阿弥とともにそれまでのもの
まね中心の能から歌舞中心の夢幻能という新しい形式を完成させ、能の芸術性を高めた。
しかし、当初の能衣装はまだ地味であったが、戦国時代の武将が戦陣の間に能を舞い茶の
湯をたしなむ風習が生まれ始めたことから、桃山、江戸時代には非常な発展を遂げた。つま
りよい時代によい環境を得て成長したわけである。
たとえば染織では、金箔・銀箔を衣装に縫いつけたり、摺り付けたり、縫箔、擦箔といっ
たテクニックが工夫され、華麗そのものであった。それは能衣装に見られるような非常にき
らびやかな、多彩な衣装であった。その派手さは武士が着ていた衣装も実にカラフルで、そ
の紋様のデザインは、現代のデザインも顔負けするくらい斬新かつ大胆なものであった。
特に片身替わりといって、一つの面の半分と半分を非常にコントラストの強いものでデザ
インするというやり方などがこの当時は、大変流行した。
|
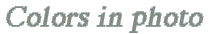
|

「三重襷花菱文半臂」(部分)
「三重襷花菱文半臂」(みえたすきはなびしもんはんぴ)
クロ−ズ・アップされたこのきれは、現存する能楽装束中で最古のものの一
つで、すばらしいデザインである。
この時代の衣装は、簡潔な素朴な中に見せる力強さ、精緻を極めた技巧など
驚嘆に値するものが多いが、それが当代の男性の、武人によって着られたとい
うことは、今やセックスレスといわれる現代においてさえ、その豪華さはより
大きな驚きであろう。
|
|

「茶碗」 曜変天目 (国宝)
「茶碗」 曜変天目(ようへんてんもく)
天目は、宗代に福建省の建窯で焼かれた茶碗の和名である。しかし、後には
他窯の茶碗でも類似のものは広義に天目と呼ぶようになった。
建窯のうち特に釉調の優れたものを曜変、油滴(ゆてき)、禾目(のぎめ)
と呼び、古来格別に賞美している。
|
|
 茶の湯 茶の湯 
ところで、前回の室町時代の色の話の終わりに、茶の湯の千利休(宗易)が室町時代の好
み、墨の色合いの侘び寂びを桃山まで引き入れたと話したが、豪華絢爛な桃山時代でも茶道
の世界だけは、派手をおさえて幾多の先人の目によってえり抜かれた道具が珍重され、それ
は今日でも変わらない。
その逸品として、日本に残る中国の茶碗「天目」を紹介しておきたい。
天目というのは、日本の留学僧が淅江省の天目山で修業し、帰国の時持ち帰った茶碗にち
なんだ名前である。最も尊ばれたのは、曜変(ようへん)天目で、本場の中国には今は1個
もなく、世界でもわが国にある3点だけである。
ここに紹介した茶碗は、その中でも抜群の出来で、トップといわれるものである。
見込み一面の漆黒釉の地に、大小さまざまの斑点が不規則に並び、その回りに美しい紅彩
が暈(かさ)状に現れている。この斑点は、金属の結晶群で紅彩は極薄の膜がプリズムの作
用をして光線を分解し、虹の光彩を放つという。比類のない名碗といえる。
外国製の茶碗の紹介が先になったが、書家であり刀剣の鑑定家でもあった本阿弥光悦が作
つた「毘沙門堂」その他、日本でつくられた由緒ある数々の名品があるが今回は割愛する。
次回の「近世日本人の色彩感覚」は、浮世絵、南画、写生画、江戸後期の「粋」な
色といったことについての話を予定している。
|
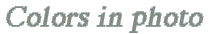
|

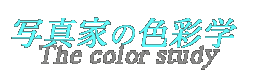 (3)
(3)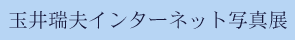
(3)
その1





