part.19 
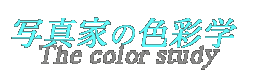 (2) (2)
|
 |
そこには、薄闇の中に美しい色光のあふれた世界が拡がる
 |
暗さになれてくると、暗順応によって内側の構造が見えてくる
|
|
上の3点の作品は、この簡素な教会の装飾的な部分の中核をなす一部として取り上げた。 前衛的な建築家として著名なルコルビュジエは、1923年ころまでの初期は絵を描き比較的遅 く1947年ころから彫刻もはじめ、タピストリ−なども手がけており、それらが総合的な表現 力として働いている。 我々がよく取材に行くヨ−ロッパの寺院、ノ−トルダムに代表されるような大寺院には大 きな色つき窓、つまり精緻を極めたステンドグラスがある。これには大聖堂と呼ばれるにふ さわしい荘重さがあるが、同時に歴史的な権威の象徴、威圧さえ感じることがある。 ルコルビュジエのこの教会は、小さな村々の教会同様に親しめるが僕が一番気に入ったの は、厚い壁をまるでナイフでスポンジケ−キでも切るように、窓の大きさも大小さまざま、 形も配置もかなり適当、勝手気ままにスパスパ切り取りとって、自分なりの創作による色つ きガラスやガラス絵をはめ込んだような素朴な手作り風の自由、闊達さであった。 この窓ガラスは、ステンドグラスではない。しかし、そこにはア−トとしての色光による 極端に簡素で美しい空間があり、それはまた教会としてふさわしい空間を創りあげていた。 僕は日本の多くの仏像に埋まった寺を写し、また外国では装飾に埋もれた教会に接してき たが、こうした祈りをささげる場所というものは、規模の大小にかかわらずイメ−ジとして は、究極的にはすべての物質的なものが消え去り、空間自体が裸形として現われ、もはやそ こは仏教的あるいはカソリック的としかいい表しえない空間が存在するところが最高であろ うと思うようになっていた。 僕は、毎日がスケジュ−ルの厳しいヨ−ロッパでの撮影行であったが、コースをはずれて 予定外の此処に来て、ぼくはさわやかな色光につつまれ、小さいが実にすばらしい祭壇を眺 めるうちに気分が安らぎ、次の旅先への期待が明るく感じられるように思えた。 この講では、色光を使った単純ともいえる型破りの造形と、きびしくやさしい美しさから ぼくが受けた感銘、つまり殆ど宗教心がなく、抹香くさいところもアーメンも縁遠い僕のよ うな者でも素直に受け入れられる、そんなところが伝わったであろうか。 |
前回は「色は感覚である。」といった概念に至る前の物理的な図解をした。 物理、化学の話は、立て続けにやると、むつかしく退屈する人もある。そこで目先を変え た話を、少し挿入しておくことにした。 色への感覚は、民族、年代、個人、教養などによって変わるといわれているが、僕たちは 感覚としての色のル−ツ、足元の日本における「色彩の時代、時代による変遷」くらいは、 常識として知っておく必要があリ、これを放置して先へすすむわけには行かない。 これまでの講座で、色の歴史としては、1000年前の王朝時代のことに触れたが、その 前後の時代による特色を、今少し常識的な解説として平易な話を進めたいと思う。 例によって僕の資料の中から、一番簡明なものとして水尾比呂志氏の著作を選び、これを 引用しながら僕の雑多な考えも加え、極端なまでに縮じめた文章にしてある。もちろん文化 史の解釈はいろいろあるが、この場合はその時代の主流についての話である。
原始時代の色は、赤 から始まった
日本の原始時代、縄文から弥生へと、殆どの土器は土の色をしているが、縄文の後期くら いになると中には赤く塗られたものがある。 これは原始信仰に関係するといわれ、だいたい世界のどの地域でも共通している。 赤色は火や血や太陽の色であり、魔を払う呪術に盛んに用いられたという。赤の強い色が ひきおこす感覚的、精神的興奮が強い力と霊的、神秘的ものを感じさせたのであろう。
図に示す弥生時代・後期の 台付塗彩壷形土器は、富田方 遺跡において発見された数多 い土器のひとつである。胴中 部以下を丹彩をもって飾りこ の地方の壷形土器の特徴をよ く表現している。 弥生文化から下って、3〜 6世紀の古墳時代には、装飾 古墳と呼ばれる石室に宗教的 な意味をもつ文様や絵画が彩 色で描かれており、やはり赤 を主体として青、白、黒、黄 といった色がいろいろな組み 合わせで使われるようになっ た。弥生時代・後期の赤い土器
繧繝彩色は、インドに起こり中 国で発達し奈良時代に日本へ渡っ てきた。 この手法は仏像ばかりでなく、 織物の仏画、器物の装飾、絵画の 立体感を出すために使われ、絵の 具の節約にもなったようである。 上代の色彩の材料は、土壌・植 物(丹、朱、黄土、茜、紅、紫、 藍)で中国模倣、五行思想にもと づく。色彩に寄せる情動は、呪術 的、霊的、神秘的な感をもち、一 色一色に関心を抱いた。秘仏 執金剛神像 (天平時代) 僕は、まだ若かった20代の初期、2年ばかり奈良に住まい、天平時代の諸仏、建物の撮 影に恵まれた。 手始めの撮影であった東大寺法華堂では仏像群に囲まれ、いつしか現実を離れ、創建時代 を体感するかのような感覚的体験をしたことがある。 東大寺法華堂の秘仏執金剛神像は、貴重な彩色を保存するために、年に1回だけ開帳され る。秘仏執金剛神像の胸当に縁どられた金地唐草や袖に残る繧繝彩色の宝相華文は非常に美 しかった。 生々しい色合いを見たあの日の光景は、腕の静脈と共に今なお鮮やかに僕の眼底に残る。 それまで天平の塑像は素材のままでも鑑賞に値すると思っていたものが、この日以降は他の 塑像もやはり多彩な装飾美が想像されるようになつたものである。
王朝時代の新しい色調
 古代から中世へ移って行く平安時代の後半、歴史では藤原時代と呼ばれる時代は、文化史 上では非常に重要な意味を持つ時代で、すでにこの講座であらましを述べた。 女性文化が全盛をきわめたこの時代でおもな役割を演じた色は、白、紫、紅であった。こ れらの色自体がもっている表情、性質は高貴であり、雅やかで、艶めかしさを備えている。 この3つの性質は、そのまま平安後期の文化を構成する要素であり、殊に紫は古代において は非常に尊い色として貴ばれ、一番美しい色、憧れの色であった。 色彩感覚の洗練、色の微妙な調子、味わいを感じ取り、見分ける力やその好みの熟成、と いったことがこの時代の特色で、色の匂いという言葉すら使われた。そういった鋭く繊細な 微妙な色彩感覚によって生み出され用いられた色、それがこの王朝時代の新しい文化を形づ くっていった。 こうした色の使い方を通じて見られる大きな特色は、どの色をとってもすべて自然の色、 自然に存在している花、木、草などがもっている色に近づけよう、人間が作り出した色を調 節していこう、という意識がはっきりと見られることである。 襲(かさね)の色目に使われている名称を見ても、その9割が自然の花の色であった。言 い換えれば自然の色に対する憧れを身につけるもの、何よりも寝殿造りという住居そのもの が外部の自然との交流をスム−ズにかつ密接におこなおうとして造られた建物であった。
古代から中世へ移って行く平安時代の後半、歴史では藤原時代と呼ばれる時代は、文化史 上では非常に重要な意味を持つ時代で、すでにこの講座であらましを述べた。 女性文化が全盛をきわめたこの時代でおもな役割を演じた色は、白、紫、紅であった。こ れらの色自体がもっている表情、性質は高貴であり、雅やかで、艶めかしさを備えている。 この3つの性質は、そのまま平安後期の文化を構成する要素であり、殊に紫は古代において は非常に尊い色として貴ばれ、一番美しい色、憧れの色であった。 色彩感覚の洗練、色の微妙な調子、味わいを感じ取り、見分ける力やその好みの熟成、と いったことがこの時代の特色で、色の匂いという言葉すら使われた。そういった鋭く繊細な 微妙な色彩感覚によって生み出され用いられた色、それがこの王朝時代の新しい文化を形づ くっていった。 こうした色の使い方を通じて見られる大きな特色は、どの色をとってもすべて自然の色、 自然に存在している花、木、草などがもっている色に近づけよう、人間が作り出した色を調 節していこう、という意識がはっきりと見られることである。 襲(かさね)の色目に使われている名称を見ても、その9割が自然の花の色であった。言 い換えれば自然の色に対する憧れを身につけるもの、何よりも寝殿造りという住居そのもの が外部の自然との交流をスム−ズにかつ密接におこなおうとして造られた建物であった。
平安時代の武家に見る色彩感覚
王朝時代の末期には、貴族文化とは別の文化が芽生えてきた。それは源氏と平家という2 大勢力に代表される武家の文化である。 武家の台頭は藤原貴族たちの勢いが傾きはじめた平安期からかたちづくられてきたが、末 期にははっきりした存在として出現してきた。この源平に代表される武家たちが好んだ色は どんな色であったか。 それはまだ貴族文化とってかわるほどのものではなく、貴族文化に習いながら武家的なも のに再生させる、作り直して行く、といった文化であった。そういう武家たちの色彩感覚は どうであったか。推理はおもしろい。それはちょうど、古代の単純であの多彩な、多様な色 彩感覚を、そっくりそのまま復活したような様相であった。 武家の色彩感覚が一番良く現れたのは、彼らの晴れ着である鎧(ヨロイ)、冑(カブト) である。平安末期から鎌倉時代にかけての甲冑はかなり残っており絢爛豪華なものである。 それは鎧の縅(オドシ)という革、竹、木の短冊のような小さい板をたくさん綴り合わせ る部分に使う革や布のひもの染色にみられる。鎧の縅の色は実にさまざまで、真っ赤な鎧、 真っ黒な鎧、紫色の鎧、紺色の鎧、あるいは小桜縅の鎧といった微妙な色の鎧。そんなもの を着て武士たちは戦場で戦ったわけである。 平家物語には、戦のありさまが描写されている場面が多いが、その中に武士が着用した鎧 の描写がある。何色縅の鎧を着ていたか、馬の毛並み、馬に置いた鞍の色なども、必ず述べ られている。 戦うことを生命とする武家たちにとって、一世一代の晴れ舞台が戦場である。そこで自分 の存在をはっきり目立たせるために、彼らは身にまとう鎧に鮮やかな色彩を使って美しい衣 装を作り出した。 こういう甲冑をみると、あの多彩であった古代がもう一度復活したように感じる。 平安貴族たちがだんだん色をぼかし、あいまいな色にしていったのに対して、武士たちは 純粋で明るい強い色をたくさん使うという特色が示されている。これは、王朝時代の末期に 現れてきた別の色彩文化であったといえよう。
鎌倉・室町時代は「黒みの時代」
ところが、中世の鎌倉時代に入ると、多彩な色がしだいにひとつの統一された色調に変化 して行く。その統一された色調というのは、黒み、黒っぽい好みであった。 これは武家というものの性格、つまり非常に強健な身体、意志を持たねばならぬという反 映であろう。鎌倉幕府の源氏三代、その後を継いだ北條氏の時代、いずれも武家は力によっ て世を統べた。そういう武家たちには、やはり華やかな色よりも強さのある色、黒みがちの 色がおのずから好みになったのであろう。 鎌倉時代になると、赤系統の縅は少なくなった中で、とりわけ好まれた代表的な色は紺色 とその同系の藍であった。赤い色も、王朝の雅びで艶やかな紅の赤さでなく、緋という赤い 色に変わっていった。これもやはり赤い色における黒みがちな好みと見ることができる。 この時代の色を表す言葉に、褐色(かちいろ)という言葉がある。褐色と書くが茶色い褐 色ではなく濃紺の色をいう。これを「かちいろ」と発音して、「かち」は「勝」に通じると ころから、とくに武家はこの色を好んだという。この褐色も濃紺だからいわゆる黒みの色で こういう色が鎌倉時代の主役を演じていたようである。
室町時代は「墨の時代」
同じ中世でも鎌倉時代から次の室町時代に移ると、また少し変化が出てくる。 室町時代を一言でいえば、「墨の時代」といえよう。 この時代の代表的な文化遺産は、周知のとおり水墨画である。水墨画はすでに鎌倉時代の 終わりころから、禅とともに中国から日本へ入ってきていたが、室町時代になると非常に盛 んになった。もちろん彩色画もあったが、主流は水墨画が占め圧倒的に流行した。
雪舟筆・達磨図 当時の京都の寺院を覗いてみると、襖には墨絵の山水、床の間にも墨絵で描かれた花や鳥 の掛物、屏風には墨絵の人物が描かれているといった調子でそれは寺院に限らずやがて武家 の館にも行われるようになった。 ところで、今日はモノクロ−ムの写真の乳剤が瞬時に示すグラデ−ションを我々は何の不 思議も感じていないが墨の色というものは、当時は非常に不思議なものに思われていたよう だ。「墨は五彩を兼ねる」といわれ、あらゆる色がその墨の中に含まれているという意味を も含んでいた。 それは単なる黒い色ではなく、墨色には薄い墨から濃い墨に至るまで、無限の段階があり 非常に微妙なニュアンスなを表すもの。そういう複雑微妙な墨色の調子を自在に駆使するの が、水墨画であったというわけである。 この水墨画を主とする時代は、ほかの色もそれに引きずられるように、暗い調子になって いった。明度や彩度が低い色彩が喜ばれ、鶸(ひわ)色とか蜥蜴(とかげ)色とかいう色が それで、また柿色などもたいへん好まれたが、これらはいずれも渋い色である。 水墨画は禅と結びつき、またお茶と結びついて、いわゆる侘(わび)の美意識をかたちづ くる大きな要素をなした。色彩の方でもあまりけばけばしい、明るい、キラキラした色は避 けられ、ト−ンの低い、落ち着いた色が好まれた。 例えば、南北朝の義満の金閣が、鎌倉的な強い輝きを象徴しているとすれば、室町中期の 義政の銀閣は、まさに渋く暗い色調の象徴である。その流れに属する千利休は、桃山時代に までこうした好みを持ち込んで行った。 次回は、「近世日本人の色彩感覚」について述べる予定。